| 01 |
|
車窓の風景 |
|

|
|
| 2002年9月21日(土)、高野山に行った。JR大阪駅から地下鉄御堂筋線に乗り換え、難波から南海特急「こうや」で1時間20分ほどで終点・極楽橋に到着。ケーブルカーに乗り、5分で山上の高野山駅に着いた。 |
|
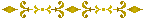
|
|
極楽橋駅
|
|

|
|
拡大写真(1024x586)163KB
|
|
|
特急「こうや」は、極楽橋に着く30分ほど前から山を登りはじめ、のろのろ運転となった。特急というのは名ばかりで、停車駅が急行よりも少ないというだけで、10分ほどしか早くならない。電化してはいるものの単線のため、途中上り電車とすれ違いのために停車する。
|
|
| 02 |
|
極楽橋〜高野山を結ぶケーブルカー |
|

|
|
写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1024x563)178KBが表示されます。
|
|
|
極楽橋駅に着いてから10分で高野山駅に着く。きわめて迅速な接続だ。
|
|
|
|
高野町 和歌山県北東部、伊都郡(いとぐん)の町。人口4774(2002)。海抜200〜1100mの連峰が累積し、総面積の90%以上を山林が占める。平均標高900mの高野山上に開けた仏教都市と1958年に編入された富貴(ふうき)の農山村部からなり、高野山は紀ノ川と有田川の分水嶺をなす。 |
| 高野町は、9世紀に弘法大師空海が開山した真言宗の総本山金剛峯寺(こんごうぶじ)を中心に発展した門前町で、現在約120の宿坊寺院と町家が並ぶ。高野山は空海の命名で山上総寺院の山号でもある。明治までは女人禁制の地で高野七口(こうやななくち)には女人堂があった。 |
| 南海電鉄高野線極楽橋駅で山上へのケーブルが接続する。参拝観光客を相手とする第3次産業が基幹産業で、宿泊施設は1万人を超す収容力を有する。 |
| 富貴地区では野菜栽培が行われる。かつては山上の寒気を利用して高野豆腐が生産された。大部分を森林が占め、林業にも依存する。 |
| 高野山一帯は高野竜神国定公園に指定され、高野竜神スカイラインが通る。金剛峯寺をはじめ国宝・重要文化財に指定された多数の文化財がある。 高野町 |
|
|
|
高野山駅
|
|

|
|
拡大写真(1024x612)116KB
|
|
|
ケーブルカーで高野山駅に着くと、奥の院行きのバスが待っていた。1日フリー乗車券を求め、すし詰め状態のバスは間もなく発車。つづら折りの道は険しく、左右に大きく揺れ、正に秘境に入る心境だった。
|
|
高野山
|
|
1200年もの間、安息を求めて数限りない人々が訪れてきた信仰の地・高野山は、陣ヶ峰、揚柳山、弁天岳など1,000m前後の山々に囲まれた海抜900m・東西5km・南北1kmの平坦地に金剛峯寺(こんごうぶじ)のほか117の寺院が建ち並ぶ一大宗教都市である。
|
|
多くの信者や遍路、先祖の墓参りに来る参詣人、四季の風情を求める行楽客、建築や彫刻の愛好家、林間学校の子供たちなど多様な人々で賑わう。
|
|
|
|
女人堂(にょにんどう)の建つ不動口(ふどうぐち)で上り坂は終わり、後は平坦な道となる。深山幽谷の地と謳われる高野山は、町中に入った限りでは、秘境とは余りにもかけ離れた歴史文化溢れる町であった。
|
|
| 03 |
|
大日如来 |
 |
|
資料 |
|
|
不動口
|
|

|
|
写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x584)179KBが表示されます。
|
|
|
高野七口の一つ・不動口。かってこの奥に女人禁制の別世界が創られた。現在、高野山駅に着いた観光客は、バスやタクシーでここから入山する。
|
|
|
|

|
|
写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x900)221KBが表示されます。
|
|
|
高野山の西端に建てられた大門は、かっては高野山の玄関口だった。宝永2年(1705)に再建され、遠く紀伊海峡、熊野連邦等を望み、我が国山岳仏教の代表的な建築物である。
|
|
|
真言宗 |
| 真言宗は、弘法大師(空海)の立教開宗による、仏教の心髄の教えを説く密教の宗派である。 |
| 密教は弘法大師によって、平安時代の初めに中国から日本に伝えられた。 |
| 密教の根本の仏は、宇宙の本体であり絶対の真理である「大日如来」であるとする。 |
|

|
|
高野山真言宗 |
| 高野山真言宗は、弘法大師を宗祖とし、金剛峯寺(こんごうぶじ)を総本山とする真言宗の中心宗派である。 |
| 弘法大師の奥の院御廟(ごびょう)を信仰の源泉とし、壇上伽藍(だんじょうがらん)を修学の地として、真言宗の教えと伝統を今日に伝えている。 |
|
|
|
女人堂
|
|
高野山の北西の入口に当たる不動口に未だ残る女人堂は、千年余りの間、女人禁制であった高野山の七つの入口(高野七口こうやななくち)に建てられた女人堂の唯一の残存建造物である。昔、女性はここから先には入ることが許されなかった。
|
|

|
|
拡大写真(1200x645)191KB
|
|
|
女人堂は、明治5年、政府により女人禁制が解かれるまで、女性のお籠り堂の役割を果たしていた。
|
|
|
|
お竹地蔵と女人道
|
 |
|
(1024x612)116KB |
|
女人堂の向かいにお竹地蔵と呼ばれる大きな地蔵が祀られている。 |
| その側に女人道の入口があり、「高野七口 女人道→」「弁天岳へ1km」の案内板が立てられている。七ヵ所の女人堂を巡りながら高野山を外から参拝するために使われた8.5kmの山道が女人道である。 |
| 近年、女人道は山仕事などにしか使われていなかったが、最近の古道ブームで女人道巡りなどが評判を呼び、女人道も整備されるようになった。 |
|
|
大 門
|
|
大門(だいもん)は、表参道である町石道(ちょういしみち)を登り切った場所に建てられた総門で、高さ25.8mの二層の楼門である。両脇に法橋運長(ほうきょううんちょう)作の金剛力士像が立つ。中国風と和風の建築様式を折衷した大型建築の傑作として、国の重要文化財になっている。
|
|
町石道は、千年の昔、弘法大師が高野山を開いたとき、木の卒塔婆(そとば)を建て、道しるべをつくった道として知られる。
|
|
| 04 |
|
深山幽谷
|
|

|
|
写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x800)193KBが表示されます。
|
|
|
|
高野龍神スカイライン中程の峠から東方の大峰山脈を望む冬景色。空海は海抜900mの山奥に平地を見つけ、真言密教の根本道場を創った。
撮影:大井啓嗣 デジタル楽しみ村
|
|
|
如意輪寺
|
|

|
|
拡大写真(1024x768)2205KB
|
|
|
金剛峯寺(こんごうぶじ)前の如意輪寺の落ち着いた佇まい。京都のお寺を見ている錯覚に駆られる。
|
|
高野山の宿坊
|
|
高野山には約120の寺院があり、4,000人が暮らしている。そのうち僧侶は1,000人いるという。寺院のうち50ヵ所余が宿坊(しゅくぼう
寺院に参詣した人の宿泊する寺坊)として信者だけでなく観光客も受け入れている。和風の個室に若い修行僧が精進料理を運び、布団の出し入れもしてくれる。各寺院の本堂での早朝のお参りのほか、写経や座禅などの体験ができる。
|
|
| 05 |
|

|
|
|
|
精進料理には名物の高野豆腐やごま豆腐が使われる。白胡麻と吉野葛(よしのくず)を丁寧に練って作られるごま豆腐は、濃厚な胡麻の風味が口いっぱいに広がり、腰があって美味い。
|
|
|
山上の町
|
|
僧侶が歩道を闊歩する山上の町・高野山。この土地は金剛峯寺が所有しており、住民は借地に家を建てて住んでいるという。
|
|

|
|
拡大写真(1024x768)218KB
|
|
|
こうやまき
|
|
高野山では、高野槙(こうやまき)の枝葉を仏前や墓前の供花として利用する。日中、道路脇のスタンドで売られている。高野槙は本槙、金松とも呼ばれ、建築材、船舶材、風呂桶等に使われる。
|
|