| 01 |
|
岸和田駅前通商店街 |
|

|
|
岸和田駅に向かって商店街があり、例年宵宮の午後パレードが行われるため、アーケードが高くつくられている。アーケードを一気に駆け抜けただんじりは、駅前で左右に分かれるため、駅前交差点が「やりまわし」と呼ばれる走りながら90度向きを変える荒技の見所となっている。
|
|
年番の法被(はっぴ)を着た自主警備員 |
|

|
|
約200年ほど前から年番制度があるという。現在年番は各町1人、当番町2人の合計23人。年番に当たった人は祭りを仕切る。この交差点には2名の警官の他に4人の年番と青年団の祭礼委員1人が配置されていた。年番は警備と書かれた赤い団扇を持ち、地車自主警備と書かれた襷をしている。 |
|
|
|
岸和田市 大阪府南部の市。大正11年(1922)に市制。人口20万4千(平成14年9月)。和泉(いずみ)海岸平野のほぼ中央にあり、市域は府県境の和泉山脈に及ぶ。建武1年(1334)楠木正成の一族和田高家(わだたかいえ)が入ったことから〈岸の和田〉と呼ばれるようになったという。 |
| 室町期に岸和田荘、戦国期に岸和田城があり、寛永17年(1640)以後岡部氏の城下町として明治に至った。また、紀州藩や岸和田藩の参勤交代路として発達した紀州街道沿いには商業地区が形成され、泉州(せんしゅう)における経済や文化の中心であった。 |
| 明治以降、和泉木綿を背景に綿紡績業が立地し、織布業や毛織物業などを含め繊維工業の町として発達した。鉄鋼、機械、レンズなどの工業もあるほか、臨海部に貯木場を中心とする木材コンビナートが昭和36年(1966)に造られ、その隣りには臨海工業用地が造成されている。 |
| 和泉山脈北麓と台地では溜池灌漑(ためいけかんがい)による米のほか玉葱、蜜柑、桃、花卉(かき)の栽培が盛んである。 |
| 関西国際空港から車で゙15分という距離にあり、大阪都心部からはJR阪和線、南海電鉄本線、阪和自動車道が通じる。「城とだんじりのまち」として知られる。 |
|
| 2002年9月14日(土)、岸和田だんじり祭の宵宮に行った。JR大阪駅から環状線内廻りで7つ目の新今宮駅で南海電車に乗り換え、急行で25分ほど。神戸・三ノ宮から1時間半ほどで岸和田駅に着いた。 |
|
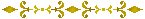
|
|
岸和田駅は西向きに駅舎があり、駅前から大阪湾に至る地域でだんじり祭が行われる。 だんじりマップ |
|

|
|
南海岸和田駅
|
| 今年は300年の節目に当たり、また、14日の宵宮・15日の本宮が土日に重なったため例年にない人出となった。 |
| 宵宮の午後1時から岸和田駅前通商店街でパレードがあるというので1時間半ほど前に到着したのだが、既に駅前は紅白の幕で囲まれた報道陣の特別席(写真上の右端)を囲んで満員状態。後方もずらりと脚立が並んでいて入り込む余地は全くなかった。 |
|
事前に岸和田市観光振興協会から情報を得ていたので、駅に沿って2ブロック南下し岸和田港塔原(とのはら)線の交差点に行ったところ、最高の位置を確保できた。
|
|
近くのコンビニで弁当を買って腹ごしらえをし、だんじりが現れるのをひたすら待った。
|
|
岸和田だんじり祭の概要
|
|
岸和田だんじり祭は、各町ごとに地車(だんじり)を保有し、子供からお年寄りまで各年齢層で役割分担を決めて組織・運営しており、祭礼年番(祭礼を司る最高組織)や岸和田市地車祭町会連合会が全体を取りまとめている。このようにしっかりした組織で運営されているのは全国でも珍しいという。
|
|
現在、岸和田駅前の旧市・岸和田地区には20町・20台、2駅北方の春木駅前の春木地区には14町・14台のだんじりがあり、合計34台のだんじりが祭りに参加する。
|
|
9月14日は早朝の曳き出しに始まり午後のパレード、夜は灯入れ曳行(えいこう)。15日の午前中には宮入りが岸城(きしき)神社(14台)、岸和田天神宮(6台)、弥栄(やさか)神社(春木地区14台)で行われる。この他、両日とも日中随時だんじりが市中を走り回る。
|
|
岸和田地区の「かんかん場(昔、船の錆落し(かんかん)をしていた所)」と呼ばれる岸和田駅西方の交差点には、ひな壇の有料観覧席(2〜5千円の指定席)が設けられている。ただし、当日券を手に入れるのは至難。
|
|
宵宮のパレード
|
|
宵宮のパレードは春木地区では午前9時半から、岸和田地区では午後1時から行われる。春木地区の春木南(はるきみなみ)だけは両方のパレードに参加するため、岸和田地区のパレードは21台のだんじりが参加する。
|
|
残念なことに、9月13日岸和田地区で試験引きのだんじりが横転し、1人が下敷きになり死亡、7人が負傷するという事故が発生した。このため今年祭りに参加するだんじりは33台となってしまった。
|
|
宵宮のパレードと本宮の宮入りの順番は、9月1日の各町の寄り合いで決められている。 パレード・宮入順番
|
|
| 02 |
 |
|
↑写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x776)218KBが表示されます。
|
|
|
|
|

|
|
|
|
大工方は祭りの華
|
|
大工方(だいくがた)は、大屋根の上で踊る花形だが、実はだんじりの目という重要な役割を担う。ハンドルのないだんじりで、ブレーキをかけて曲がるきっかけを作るのはだんじり前方の前梃子(まえてこ)だが、方向転換はだんじり後方の後梃子(うしろてこ)が行う。後梃子は前が見えないため、大工方の合図により舵を取る。
|
|
|
春木南のだんじり
|
|
午後1時過ぎ、パレードのトップを切ってアーケードを駆け抜けた春木南のだんじりが姿を現した。
|
|

|
|
拡大写真(990x850)170KB
|
|

|
タオル地の赤い捻り鉢巻に「春木南」と赤く染め抜かれた黒の法被(はっぴ)に白のパッチ。岸和田一といわれる大型だんじり。
|
|
大屋根枡合(ますあい
大屋根下の正面)の忠臣蔵「刃傷松の廊下」の彫物が自慢だ。
|
|
ひたすら走る祭り
|
|
大勢の引き手が引き綱を持って交差点を駆け抜けるエネルギーには圧倒される。老若男女がひたすら走る。京都の葵祭や祇園祭のような優雅なパレードではない。あっという間に目の前を通り過ぎてしまう。町民が交代で一日中走り回るので、ヘトヘトになる。これは正に体力勝負の祭りである。
|
|
祭りは、盆と正月が一度に来るような感じで、町をあげて盛り上がる。地元の会社や商店はもちろん小中学校も休校となる。郷里を離れている人もこの日だけは帰ってくる。岸和田出身の指名手配犯の検挙率が高いのもこの祭りの時期だという。市内は正に祭り一色である。
|
|
だんじりの曳行には、纏(まとい)、引き方、前梃子(まえてこ)、鳴り物、大工方(だいくがた)、後梃子(うしろてこ)などの配置がある。それぞれ町内の子供会、青年団などが分担する。だんじりの役割分担
だんじり各部の名称 |
|
| 03 |
|
走る走る! 各町によって多少の差があるが、試験曳きも含めだんじりとともに走る距離は4日間で何と約60km!青年団はだんじり曳行に備え、8月頃からランニングをして鍛えているという。
|
 |
|
写真をクリックすると新しい窓が開き(1200x900)229KBが表示されます。
|
|
|
大工方の飛行機乗り |
 |
|
写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x640)182KBが表示されます。
|
|
|
|
だんじりがやってくると笛や鉦・太鼓の音と引き手による「そーりゃ!そーりゃ!」のかけ声が怒濤の如く押し寄せ、町中に響き渡る。
|
|
1台のだんじりが来るとすぐに走り去ってしまうので、次のだんじりが来るまでにかなり間が空いてしまう。しかし、この感想はこの交差点でのことで、このあと「らんかん橋」に行ったことで的外れであることが分かった。
|
|
本町のだんじり
|

|
続いてパレード2番手の本町(ほんまち)がやってきた。引き方は白の捻り鉢巻、本の一字を赤く染め抜いた黒の法被に黒の腹掛け・パッチ、黒の地下足袋で統一。
|
|
大工方のみ白のパッチで注意を引きつける。何といっても大屋根大工方の飛行機乗りが有名。
|
|
昭和7年(1932)、京都西陣での万国博覧会にだんじり正面下部の大連子(おおれんじ)・小連子(これんじ)の彫物を出品し、見事第1位に輝いたという。平成8年(1996)秋には、伊勢神宮2000年祭に町をあげて参加した。
|
|
|
|
|
|
自慢のだんじり
|
|
各町自慢のだんじりは、総欅(けやき)造りでおよそ重さ4ton、高さ3.8m、幅2.5m。全て釘を使わずに組み立てられている。
|
|
周囲の彫り物は、源平合戦、大坂夏の陣など歴史に残る戦記や神話などの名場面を彫り上げた力作揃いで、人や動物など精巧で力強い。
|
|
| 04 |
|
堺町・大工方のジャンプ
|
 |
|
写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1024x768)161KBが表示されます。
|
|
|
|
|
大屋根の上でリズミカルに踊る大工方は、岸和田っ子の憧れの的だ。
|
|
|
2本の引き綱の長さは100〜200m、引き手は500〜1,000人と大勢。
だんじりを新品であつらえると1億円はかかるというから驚きだ!
|
|
堺町だんじり
|

|
パレード6番の堺町(さかいまち)がやってきた。法被は綱先から後梃子に至るまで、全員が煉瓦格子の図柄に統一している。
|
|
現在の法被は昭和39年から続いている。
|
 |
|
拡大写真(1024x674)102KB
|
|
|
堺町は大工方だけが白一色に身を包んでいる。大屋根の上で男前の兄貴が格好良くポーズをとる。
|
|
| 05 |
|
大屋根の大工方
|
|
|
|
写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真が表示されます。
|
 |
|
 |
|
紙屋町 (1024x768)155KB |
|
大手町 (1024x768)147KB |
|
|
|

|
紙屋町:かみやちょう
平成3年完成。旧市20町の中で平成に造られただんじり第1号。大屋根正面の鬼板に眼下を睥睨(へいげい)する獅咬(ししかみ)の彫物は豪快。
|

|
大手町:おおてちょう
昭和15年完成。彫物師・和泉彫、黒田一門・木下舜次郎の出世作であり、彫物の力強さはみごと。正面と後ろ姿が美しく、姿千両と賞賛される。
|
|
|
 |
|
 |
|
上 町 (1024x768)159KB |
|
藤井町 (1024x768)117KB |
|
|
|
|
|

|
上 町:うえまち
昭和3年欅(けやき)材を大量に集め良材のみを選び出して製作したので、余った材料で立派なだんじりが3台もできあがったという贅沢なもの。
|

|
藤井町:ふじいちょう
平成5年完成。彫物師松田正幸の力作により、土呂幕(どろまく)から見送りまで、信長公記で統一されている。
|
|
|
腹掛け・パッチの子供たち
|
 |
|
拡大写真(1024x768)120KB
|
|
|
だんじり衣装の腹掛け・パッチ(patchi
股引)は、昔からの職人の仕事着だ。今は、ジーンズと同じ感覚で着こなす。素材は綿100%ではき心地が良く、丈夫で動きやすいという。
|
|

|
|
岸和田港塔原(とのはら)線
|
 |
|
拡大写真(1024x768)194KB
|
|
露店の数は、日本一といわれるほどに多い。
|
|
|