|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浄瑠璃という名称は、源氏の大将・義経の恋人の名前に由来するという。慶長末年(1615)に記録された「十二段さうし」(作者不詳)によると、牛若丸(義経)が平家討伐のため奥州に下る途中、三河国矢作(やはぎ)で浄瑠璃姫という美女に出会う。 |
|
|
姫の父親は三河の国主、母親は海道一の遊女だが、子供がなかったので、峰の薬師に祈願して女の子を授かった。女の子はその美しさから「浄(きよ)らかで瑠璃(玉)のような姫」と名付けられた。 |
|
|
ある夜、浄瑠璃姫は多くの侍女たちと楽器の演奏を楽しんでいたが、笛がなかった。すると、垣根の外で聴いていた牛若丸が演奏に合わせて笛を吹き、それが縁で二人は結ばれた。 |
|
|
牛若丸は再び旅に出るが、その途中、病気で瀕死の状態に陥る。しかし、八幡の神の加護と浄瑠璃姫の必死の介抱で全快し、平家討伐の後に会おうと約束して別れる。 |
|
|
この物語を語るすべての芸能が「浄瑠璃(節)」と称され、のちに別の物語を語る場合にも浄瑠璃の名が使われるようになったという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お弓・お鶴別れの銅像
|
| 阿波十郎兵衛夫妻は、名刀「国次」をさがす為大坂、玉造に隠れ住んでいた。ある日、巡礼姿で、はるばる訪ねてきた娘に国はいずこと尋ねれば、阿波の徳島、して父さんの名は、阿波の十郎兵衛、母さんはお弓と申します 聞いてびっくり、さては我が子か、なつかしやと名乗りあげたい胸の内、なれど悲しい隠れの身、可愛い我が子まで罪を負わせたくない母親の情愛、すごすごと立ち去る後姿に、もう一度顔を引き寄せ、涙する哀情切々たる情景である。 |
|
|

|
|
拡大写真(1200X900)287KB
|
|
|
|
|
|
|
映画等の新たな娯楽の登場や戦争の影響で一時急速に衰えた人形浄瑠璃は、昭和28年の財団法人阿波人形浄瑠璃振興会の結成などを契機として、徐々に復興してきた。 |
|
その後民俗文化財として見直されるようになり、平成11年(1999)に阿波人形浄瑠璃が「国指定重要無形文化財」に、平成14年(2002)には人形師・天狗久(てんぐひさ)の制作用具・製品等が「国指定重要有形民俗文化財」に指定された。 |
|
|
|
|
|
|
|
資料館
|
|
屋敷の資料館には、人形浄瑠璃に使われる木偶(でく)人形や人形首(かしら)が多数陳列されている。
|
|
|
|
|
|
|
|
人形首
|
|
|
| 初代天狗久(てんぐひさ)の最大の功績は、舞台道具の一部と見なされていた人形浄瑠璃芝居の人形首を芸術の域にまで高めたことであるといわれる。 初代天狗久 |
|
|
 |
|

|
| |
|

|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
木偶でく人形
|
|

|
|
拡大写真(1200X1000)143KB
|
|
|
|
十郎兵衛の遺品
|
| 十郎兵衛が処刑されたと同時に長男、二男、三男の三人の男子は同日に処刑され、妻お弓、娘お鶴は隣国へ追放された。屋敷は、蜂須賀侯から鳴門土佐泊浦の沢口助之丞に渡し、その子孫がこの家、屋敷を継いだ。 |
| この住家の二階奥深く「あけずの箱」と言い伝えられている箱があった。若しこれに手を触れると凶事があると言われ、家人も恐れて一度も内を改めたことがなかった。 |
| 鎧櫃大の箱は煤にうずもれて、ただ宝物として伝えて来たが、大正初年に川内村郷土誌を作るため、当主沢口勘吾の許しを得て郷土誌編さんの人々と神官などが立会の上、あけずの箱の内を改めたところ、中から鎧、刀や古文書などが出て来た。さらに十郎兵衛が日常使用していた「秤」や「手文庫」その他の品々とお弓の使用していた櫛・甲がい、鏡、簪などが出て来た。 |
|
|

|
|
拡大写真(1200X800)126KB
|
|
|
|
|
|
|
|
文楽(ぶんらく)とは、大坂の人形浄瑠璃芝居の呼称である。義太夫節を地とし3人遣いの人形で演じる。大坂において義太夫節を地とする人形芝居は、貞享年間(1684‐88)竹本義太夫によって創立された竹本座に始まるが、その後いくたびかの盛衰をへて幕末には植村文楽軒による興行が代表的な存在となった。 |
|
|
1872年、新開地の松島に移ると同時に文楽座を名のり、これに対抗して旗揚げした彦六座の芸系が大正期に滅び去ったあとは文楽座がただ一つの存在となり、〈文楽〉はこの芸能自体を意味するようになった。 |
|
|
現在では文楽は日本の人形劇の代表的存在として能、歌舞伎と並んで三大国劇の一つに数えられ、1955年には国の重要無形文化財の指定(団体)を受け、さらに1963年に国と大阪府・市などにより財団法人文楽協会が設立されて、補助金によって運営されるようになった。1984年には大阪に専用の国立文楽劇場が開設された。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鶴亀の庭
|
|
木漏れ日の下で、かっての板東家の庭を観賞する。300年前の悲劇や人形浄瑠璃の悲しい物語の余韻を噛みしめる。
|
|
|

|
|
拡大写真(1200X900)245KB
|
|
|
|
阿波十郎兵衛一家の悲劇と、「傾城阿波の鳴門」という物語は、登場人物が同じ名前というだけで、全く関係がない。しかし、実在の人物である十郎兵衛の屋敷が今日まで存続し、その屋敷の一角で、この家族が登場する人形浄瑠璃が演じられている。なんとも不思議なことである。 |
|
|
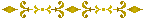
|
|
|
 |
|
《 撮影 2002年8月13日
》
オリンパス
CAMEDIA E-20 500万画素
ワイド・エクステンションレンズ使用
120枚 140MB
|
|
|
|
人形浄瑠璃の里として知られる阿波の国・徳島では、今日でも伝統芸能として人形浄瑠璃が継承されている。 |
| 細々という形容詞が適切かも知れない。それほど今日我々の目に触れる機会は少なくなっている。残念なことである。 |
| 阿波踊りの隆盛を思うとき、祭り見物に来た観光客に人形浄瑠璃の素晴らしさをもっとアピールすべきだと思う。そして我々も日本の素晴らしい伝統に、もっと関心を寄せるべきであろう。〈 完 〉 |
|
|
|
|
|
|