|
|
|
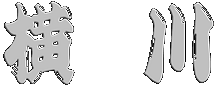 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無動寺坂を引き返し、ケーブル延暦寺駅前を通って東塔(とうどう)のシャトルバス乗り場に到着。比叡山ではタクシーが使えないので、移動はバスか徒歩となる。長距離移動はシャトルバスを利用することにしてバスに乗り、比叡山内1日フリー乗車券(800円)を購入し、一気に6km先の比叡山北部に位置する横川(よかわ)に行った。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舞台造りの横川中堂 |
|

|
|
拡大写真(1200x900)349KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
横川は叡山三塔の中で最奥の比叡山北端に位置し、大原に近いところにある。無動寺谷ほどではないが寂しいところである。かつて横川を拓いた第三代天台座主・慈覚大師円仁(じかくだいし・えんにん)や延暦寺中興の祖として知られる慈恵大師良源(じけいだいし・りょうげん)が隠遁の地としたように、あらそいごとや俗事から離れて修行するには適地であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
朱塗りの横川中堂 |
|

|
|
拡大写真(1600x1100)404KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
横川に入って最初に見えてくるのが朱塗りの舞台造りで知られる横川中堂で、嘉祥元年(848)、円仁(えんにん)が根本観音堂として創建したものである。昭和17年(1942)の落雷で焼失したが、昭和46年(1971)に再建された。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
観音像の奉納 |
|

|
|
拡大写真(1400x1050)281KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
堂内は一周できるようになっており、三方から内陣を覗くことができる。本尊・木造聖観世音菩薩(せいかんぜおんぼさつ)立像(聖観音)は平安時代の作といわれ、国の重要文化財に指定されている。横川中堂は、新西国三十三箇所観音霊場第十八番札所ともなっている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
本尊・聖観音にお参りする夫妻 |
|

|
|
拡大写真(1600x1160)207KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高浜虚子が延暦寺に滞在した経験を基に書いた風流懺法( ふうりゅうせんぽう )で延暦寺と縁ができ、横川中堂が雷火で焼失した際、多額の見舞金を送ったことから、昭和28年(1953)文学碑・虚子の塔が建てられた。近くに虚子の句碑がある。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
拡大写真(1400x950)279KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元三大師堂は、古くは定心房(じょうしんぼう)とも云われ、天台宗中興の祖といわれる慈恵大師良源(元三大師)の住房の跡をついだもの。はじめは弥勒菩薩を本尊としたが、現在は元三大師の画像を本尊にしており、元三大師堂、俗に「横川のお大師さん」と呼ばれる。元三とは慈恵大師の入寂が正月三日だったことによる。 |
|
|
|
康保4年(967)、村上天皇の命により、法華経の論議法要が春夏秋冬に行われたので、四季講堂とも呼ばれる。正面が本堂。左の僧坊に回峰行で使われた草鞋がぶら下がっている。おみくじ発祥の寺としても知られる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元三大師堂(四季講堂) |
|

|
|
拡大写真(1400x1050)342KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永観2年(984)全国に疾病が流行し、ちまたでは疫病神が徘徊し、多くの人々が次々と全身を冒されていった。元三大師は、これを救おうと、大きな鏡の前に自分の姿を映し、静かに目を閉じ禅定(ぜんじょう 座禅)に入ると、大師の姿は段々と変わり、骨ばかりの鬼(夜叉 やしゃ)の姿になった。 |
|
|
|
見ていた弟子の中でただ一人明普阿闍梨だけがこの姿を写し取った。大師は写し取った絵を見て版木でお札(おふだ)に刷らせ、各家の戸口に貼り付けさせたところ、病魔が見事に退散した。 |
|
|
|
やがてこのお札のあるところ病魔は恐れて寄りつかず、一切の厄難から逃れることができたので、以来千余年、このお札を角大師と称し、元三大師の護符としてあらゆる病気の平癒と厄難の消除に霊験を顕(あらわ)し、全国的に崇められているという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
角大師の護符 |
|

|
|
拡大写真(1400x1050)383KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元三大師堂の南方に恵心院がある。日本の浄土教の祖・恵心僧都源信(えしんそうず・げんしん)の旧跡といわれ、源信はここに籠もって仏堂修行と著述に専念し、浄土教の基礎を創ったという。 |
|
|
|
極楽浄土の思想は、法然の浄土宗や親鸞の浄土真宗の根幹をなすものであるが、その源流をたどれば、寛和元年(985)仏教の経典や論書などから多くの重要な文章を集めた往生要集に行き着く。源信は、死後に極楽往生するには、一心に仏を想い念仏の行をあげる以外に方法はないと説いた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ひっそりと建つ恵心院 |
|

|
|
拡大写真(1200x900)386KB
|
|
|