|
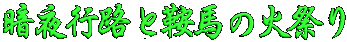
|
|
| 志賀直哉は、大正10年(1921)から11年にかけて発表した彼の代表作《暗夜行路》の中で、鞍馬の火祭りを取り上げている。主人公の時任謙作が京都の衣笠村(京都市の金閣寺の近く)に住んでいるとき、この祭りを友人とともに見物した。後編の十七に4ページにわたって詳細な描写がある。(新潮文庫
363〜366ページ) |
|
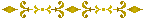
|
| 十月の下旬のある日、謙作は末松、水谷、水谷の友達の久世などと鞍馬に火祭と云うのを見に行った。日の暮れ、京都を出て北へ北へ、幾らかの登りの道を三里程行くと、遠く山の狭(はざま)がほんのり明かるく、その辺一帯薄く烟(けむり)の立ちこめているのが眺められた。苔の香を嗅ぎながら冷え冷えとした山気を浴びて行くと、この奥にそう云う夜の祭のある事が不思議に感ぜられた。子供連れ、女連れの見物人が提灯をさげて行く。それを時々自動車が前の森や山の根に強い光を射つけながら追い抜いて行く。山の方からは五位鷺が鳴きながら、飛んで来る、そして行く程に、幽(かす)かな燻(いぶ)り臭い匂いがして来た。 |
| 町では家毎(ごと)、軒先に──と云っても通りが狭いので、道の真中を一列に焚火が並んでいた。大きな木の根や、人の背丈け程ある木切れで三方から囲い、その中に燃えているのが、何か岩間の火を見るような一種の感じがあった。 |
|
焚火の町を出抜けると、稍(やや)広い場所に出た。幅広い石段があって、その上に丹塗(にぬり)の大きい門があった。広場の両側は一杯の見物人で、その中を、褌(ふんどし)一つに肩だけ一寸(ちょっと)した物を着て、手甲、脚絆、草鞋(わらじ)がけに身を固めた向う鉢巻の若者達が、柴を束ねて藤蔓(ふじづる)で巻いた大きな松明を担いで、「ちょうさ、ようさ。──ちょうさ、ようさ」こういう力ン(りきん)だ掛声をしながら、両足を踏張り、右へ左へ踉蹌(よろ)けながら上手に中心を取って歩いている。或る者は踉蹌ける風をして故(わざ)と群衆の前に火を突きつけたり、或る者は家(うち)の軒下にそれを担ぎ込んだりした。火の燃え方が弱くなり、自分の肩も苦しくなると、一ト抱え程あるその松明を不意に肩からはずし、どさりと勢よく地面へ投げ下ろす。同時に藤蔓は撥(はじ)けて柴が開き、火は急に非常な勢いで燃え上がる。若者は汗を拭き、息を入れているが、今度は又別の肩にそれを担ぐ。それも一人では迚(とて)も上げられず、傍(そば)の人から助けて貰うのである。
|
|
|
| この広場を抜け、先きの通りへ入ると、其所(そこ)にはもう焚火はなく、今の松明を担いだ連中が「ちょうさ、ようさ」という掛声をして、狭い所を行き交う。子供は年相応の小さい松明を態(わざ)と重そうに踉蹌けながら担ぎ廻った。町全体が薄く烟り、気持ちのいい温もりが感ぜられる。 |
| 星の多い、澄み渡った秋空の下で、こう云う火祭を見る心持ちは特別だった。一ト筋の低い軒並の裏は直ぐ深い渓流になっていて、そして他方は又高い山になっていると云うような所では幾ら賑わっていると云っても、その賑かさの中には山の夜の静けさが浸透(しみとお)っていた。これが都会のあの騒がしい祭りより知らぬ者には大変よかった。そして人々も一体に真面目だった。「ちょうさ、ようさ」この掛声のほかは大声を出す者もなく、酒に酔いしれた者も見かけられなかった。しかもそれは総(すべ)て男だけの祭である。 |
| ある所で裸体(はだか)の男が軒下の小さな急流に坐って、眼を閉じ、手を合わせ、長いこと何か口の中で唱えていた。清いつめたそうな水が乳の辺りを波打ちながら流れていた。大きな定紋のついた変に暗い提灯を持った女の児(こ)と無地の麻帷子(あさかたびら)を展げて持った女とが軒下に立ってその男のあがるのを待っていた。漸(ようや)く唱え言を終わると男は立って、流れの端しに揃えてあった下駄を穿(は)いた。帷子を持った女が濡れた体に黙ってそれを着せ掛けた。男は提灯を待たず、下駄を曳きずって直ぐ暗い土間の中へ入って行った。これはこれから山の神輿を担ぎに出る男であるという。 |
| こう云う連中が間もなく石段下の広場に大勢集まった。其所には二本の太い竹に高く注連縄(しめなわ)が張渡してあって、その注連縄を松明の火で焼切ってからでなければ誰もその石段を登ることができないとの事だ。しかし縄は三間より、もっと高い所にあって、松明を立ててもその火は却々(なかなか)達(とど)きそうにない。沢山の松明がその下に集められる。その辺一帯、火事のように明かるくなり、早くそれの焼切れるのを望み、仰向いている群衆の顔を赤く描き出す。 |
|
やがて、漸く火が移り、縄が火の粉を散らしながら二つに分かれ落ちると、真先に抜刀(ぬきみ)を振翳した男が非常な勢で石段を駆登って行った。直ぐ群衆は喚声をあげながら、それに続いた。然し上の門にもう一つ、それは低く丁度人の丈より一寸高い位に第二の注連縄が張ってある。先に立った抜刀の男はそれを振翳した儘(まま)駆け抜ける。注連縄は自然に断(き)られる。そして群衆は坂路を奥の院までその儘駆け登るのである。
「どうだい、もう帰ろうか」と謙作は末松を顧みて云った。
「お旅でやるお神楽を見て行こうよ」
神楽というのは四五人で担ぐような大きな松明を幾つか、神楽の囃子に合わせて、神輿の囲りを担ぎ廻るのである。
「大概もう分かったじゃないか。早く帰って寝て置かないと明日の音楽会で参るぜ」
「何時だ──二時半か」時計を見ながら末松が云った。
「これで京都へ帰ると丁度夜が明けるかも知れませんよ」と水谷が云った。
「それじゃあ、帰るか」末松は未練らしく云った。「神輿を下ろす時が却々勇ましいそうだ。坂だから段々早くなるので、太い縄をつけといて、それを女が大勢で逆に引張るのだそうだ。この祭りで女の出るのはそれだけなんだ」
「兎(と)に角帰りましょう。夜が明けてから三里、陽に照らされて歩くのは想いですよ(注)」と水谷が云った。
|
| 末松も納得した。焚火の町では、来る時、岩間の火のように見えていたのが今は盛んに燃えていた。町を出ると急に山らしい冷気が感ぜられた。四人は時々振返って、明るい山の狭(はざま)を見た。道は往きより近く思われ、下りで楽でもあったが、矢張り皆は段々疲れて、無口になった。 |
| 京都へ入る頃は実際水谷が云ったように叡山の後ろから白ら白ら(しらじら)と明けて来た。出町の終点で四人は暫く疲れた体を休めた。間もなく一番の電車が来て、それに乗り、謙作だけは丸太町で皆と別れ、北野行きに乗換え、そして秋らしい柔らかい陽ざしの中を漸(ようや)く衣笠村の家(うち)に帰って来た。 |
|
(注)想いですよ:いかにも気が重いことだ、の意 |
|
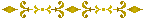
|
| 全文を忠実に掲載した。作者の細やかな観察眼はさすがプロだと感心する。暗夜行路が書かれた大正時代の火祭りは、夜中の1時2時に行われていたのだろうか。祭リの掛け声を「ちょうさ、ようさ」と表現しているが、現在では明らかに「さいれーや、さいりょう!」という。大正時代から現在までの間に掛け声が変化したとは考えられないので、作者の記憶違いかと思われる。 |