|
|
|
|
|
|
三 尾
|
|
|
|
高雄付近観光案内図 |
 |
|
拡大写真(800x1600)197KB
|
|
|
2002年11月16日(土)、JR京都駅からバスに乗り、周山街道(しゅうざんかいどう)とよばれる国道162号線沿いにある洛西の三尾(さんび)に行った。
|
|
京都市右京区梅ヶ畑(うめがはた)にある栂尾(とがのお)・槙尾(まきのお)・高雄(高尾)(たかお)を総称して三尾と呼び、渓谷・紅葉・古刹(こさつ)の名所として知られる。高雄といった方が名が通っていて分かりやすい。
|
|
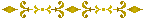
|
|
京都駅前を出発して約50分、栂尾(とがのを)というバス停で下車した。三尾の一番奥である。 |
|
世界遺産に登録されている栂尾の高山寺(こうざんじ)を皮切りに、清滝川(きよたきがわ)を下りながら槙尾の西明寺(さいみょうじ)、高雄の神護寺(じんごじ)を巡った。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栂尾の山紅葉
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)290KB
|
|
|
|
|
|
|
栂尾山高山寺
|
|
|
|
国宝・明恵上人樹上座禅像 |
 |
|
拡大写真(800x1600)197KB
|
|
|
北山杉(きたやますぎ)の里にある高山寺は、山号を栂尾山といい、古義真言宗(こぎしんごんしゅう)の別格本山である。寺地は清滝川の清流に臨み、寺域は老木に覆われ、紅葉の名所である。
|
| 鎌倉時代の初め、この地にあった天台宗の古刹・度賀尾寺(とがのおでら)が神護寺の文覚(もんがく)上人によって復興され、神護寺の別院となった。 |
| しかし、間もなく荒廃し、建永元年(1206)、後鳥羽上皇の命を奉じた明恵(みようえ)(のちの高弁)上人が華厳宗興隆の道場として再興したのが、現在の高山寺の始まりである。 |
|
それ以後、朝廷や幕府の崇信も厚く、建物や寺領の寄進も続いたが、応仁の乱で衰微(すいび)し、近世になって豊臣・徳川両氏の保護もあって寺観もやや整備され、これまでの華厳・真言の兼宗をやめて真言宗に転じた。 高山寺 明恵上人
|
|
|
|
|
| あかあかやあかあかあかやあかあかや あかあかあかやあかあかや月 明恵上人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石水院 |
|
空を覆う山紅葉 |
 |
|
 |
|
拡大写真(1200x900)174KB
|
拡大写真(1200x900)354KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石水院
|
|
|
|
入山して直ぐ右の国宝・石水院は、明恵上人が後鳥羽上皇の学問所だった所を住居としていた建物で、簡素な造りが特徴である。明恵上人樹上座禅像の写し、鳥獣戯画の写し、善財童子像などが展示されている。
|
|
|
|
|
|
|
明恵上人樹上座禅像 国宝・明恵上人樹上座禅像は、上人の容貌や周囲の自然が生き生きと描かれた写実的な絵として知られる(写真前出)。 |
|
|
|
鳥獣戯画(ちょうじゅうぎが) 国宝・鳥獣戯画は、高山寺に伝わる4巻一組の白描絵巻で、人物の戯画も含み、鳥獣人物戯画ともいわれる。鳥羽僧正( とばそうじょう )筆として名高いが、各巻ごとに内容や画風を異にし、制作時期も12世紀中ごろのものから13世紀中ごろまで相前後することから、3・4巻は別人の筆によるとの説がある。実物は、東京と京都の国立博物館に保存されている。
|
|
|
|
有名な猿、兎、狐、蛙などを擬人化して遊戯や法会の場面を描いた甲巻と、牛や馬など身近な動物の生態を生々と写し出し、麒麟、竜など空想上の動物をも加えて粉本風に羅列的に描きつづけた乙巻の2巻は、墨一色の濃淡、強弱自在な筆さばきをみせて表現力に富む。
|
|
|
|
善財童子(ぜんざいどうじ) 華厳経・入法界品(にゅうほっかいぼん
菩薩の修行の段階を表した編)の主人公。サンスクリット名はスダナ
Sudhana。母の胎に宿ったとき、財宝が家中に満ちたことから名づけられたという。
|
|
|
|
福城(ダーニヤーカラ)の豪商の子で、福城の東、荘厳幢娑羅林(しようごんどうさらりん)で文珠(マンジュシュリー)菩醍(ぼさつ)の説法を聞いて仏道を求める心を発し、その指導によって南方に53人の指導者を訪ねて遍歴し、再び文珠のもとに戻り、最後に普賢(サマンタバドラ)菩醍(ぼさつ)の教えによって修行を完成した。善財童子は修行者の理想とされ、後の仏教文化に大きな影響を与えたという。
|
|
|
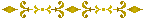
|
|
|
高山寺は、古くから文化財の宝庫といわれ、鎌倉時代を中心として国宝・重要文化財は一万余点にも及ぶ。 |
|
|
鳥獣戯画(国宝/鎌倉時代)
|
 |
|
拡大写真(1200x760)96KB
|
|
|
善財童子 |
 |
|
拡大写真(800x825)75KB
|
|
|
|
|
石水院の縁側から間近に見る紅葉の森が素晴らしい。その向こうの清滝川対岸の山や北山杉の山々も・・。太陽の光が眩しいほどに射し込み、のどかな秋のひととき。騒々しい京都中心部の古刹とは比べものにならないほど、静寂な時がゆったりと流れていた。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石水院の縁側
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)288KB
|
|
|
|
|
|
|
日本茶の発祥地 |
|
|
| ひくらしやここにいませし茶の聖 水原秋桜子(みずはらしゅうおうし1892-1981) |
|
|
|
| 茶道史の上では、栂尾は日本茶の発祥地で、日本最古の茶畑がある。臨済宗の開祖・栄西(えいさい)禅師から中国の茶の種子を贈られた明恵上人が山内にこれを植えたのがはじまりである。 |
|
| それ以来、栂尾産の茶は中世を通じて本茶(ほんちや)と呼ばれ、栂尾以外でとれる非茶(ひちゃ)と区別されて珍重された。 |
| この茶が宇治にも広がり、宇治茶となった。現在も宇治の茶業者が毎年新茶を上人の御廟に献茶しているという。 |
|
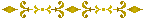
|
|
石水院を出て山を登ると、鬱蒼とした北山杉の林の中に、開山堂、明恵上人御廟、金堂などが点在する。
|
|
 |
|
(600x800)180KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鮮やかな山紅葉
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)310KB
|
|
|
|
|
|
開山堂
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)316KB
|
|
|
|
明恵上人御廟
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)307KB
|
|
|
|
北山杉の中の金堂
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)285KB
|
|
|
|
清滝川に架かる指月橋
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)288KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西明寺
|
|
|
|
高山寺と神護寺の間に位置する西明寺は、古義真言宗に属し、槇尾山(まきのをさん)と号す。天長9年(832)に空海の高弟・智泉大徳(ちせんだいとく)が神護寺の別院として開いた。清滝川に架かる指月橋(しげつきょう)は、西明寺の入り口で、観光客の記念撮影のスポットとなっている。境内に入ると紅葉の真っ盛りであった。 西明寺
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西明寺客殿
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)318KB
|
|
|