|
|
|
|
|
|
|
|
▲▼ 岡山城の金鯱(きんしゃち/きんのしゃちほこ)は、金箔押鯱瓦(きんぱくおし・しゃちがわら)である。これは粘土製の素焼きの鯱瓦に漆を塗り、金箔を施したもの。他に、広島城大天守や松本城大天守など豊臣恩顧と呼ばれる大名の居城に見られる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1200X1600)207KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ 金鯱と云えば名古屋城の金鯱が有名だが、当時、純金 215.3kg の金が使用されていたという。高さは約2.6mあり、日本一の大きさである。尾張藩の財源として二度、換金のために鱗部分の金板が剥がされ、そのつど低品位の鱗と換装されている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名古屋城の黄金の鯱(雄) |
|

|
|
拡大写真(1200x940)224KB 【E-1
566mm F11.0 1/1250秒 ISO200
】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▲ その際、輝きの低さから改鋳したことが露見することを恐れ、盗難防止という口実で金網で覆ったこともあるという。事実、盗難も二回ほどあったらしい。徳川の金鯱の中では最も長く現存していたが、昭和20年(1945)に空襲で焼失し、現在のものは、復興天守建造のときに、大阪の造幣局の地下室で製造されたもの。 金鯱の名古屋城 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
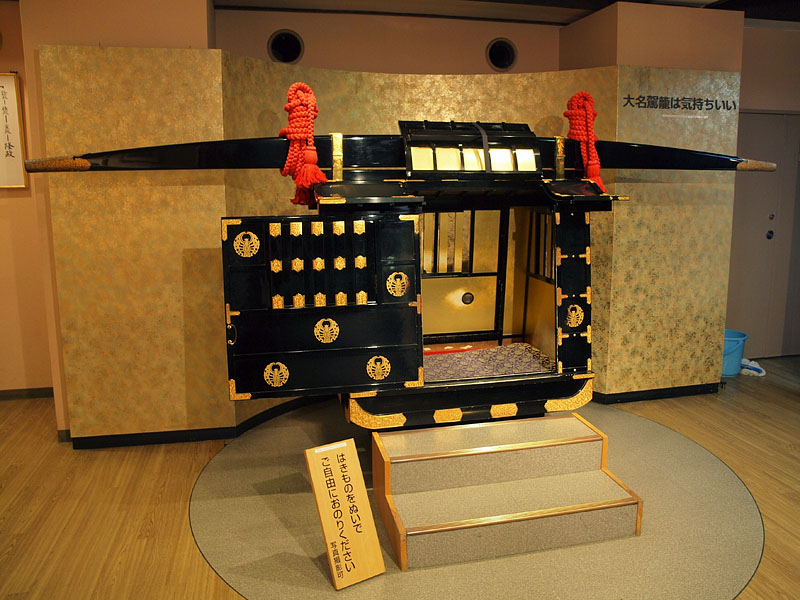
|
|
拡大写真(1600X1200)303KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ 同店のPR広告 : 岡山城天守閣の一階にある茶店です。旅のつかれに一休みして頂けるお店。岡山城名物“珈琲ぜんざい”は一度は、飲んで頂きたい商品です。お砂糖のかわりに粒あんを入れてお召し上がり下さい。夏は“アイス珈琲ぜんざい”もあります。オリジナリティあふれるメニューに、おもわずびっくりな、そんなお店です。岡山にお越しの節は一度お越し下さいませ。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1600X1000)274KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ 廊下門(ろうかもん)は、本丸の北側から中段に上るための裏門に当たる。本段の張出部から中段にかけて上屋が渡され、その下に門扉を設けた櫓門の型式をとっている。上屋は、本段御殿に住む藩主が中段の表書院に降りる道筋に当たり、この門の名の起こりとなった。 |
|
|
月見櫓と同じく1620年代に池田忠雄によって建てられたものであるが、明治になって取り壊された。現在のものは、昭和41年(1966)に鉄筋コンクリートで再現されたものである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1600X1070)456KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1250X1600)316KB
|
|
|
|
|
|
|
こうようの みずもにはゆる うじょうかな |
|
The Crow Castle, colored leaves being reflected in the water. |
|
The Crow Castle being reflected in the water of colored leaves. |
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1800X1350)456KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
一級河川・旭川(あさひがわ)は、岡山県中央部を流域とする旭川水系の本流で、吉井川(よしいがわ)と高梁川(たかはしがわ)と並ぶ岡山三大河川の一つに数えられる。支流は146、それらを含めた河川総延長は821.9kmにのぼる。 |
|
|
上流域では中国山地を流れて深い谷を形成し、中流域では吉備高原のなだらかな丘陵地や扇状地性の落合盆地などを形成しながら蛇行している。下流域では川の堆積作用や干拓によって岡山平野が形成され、最後は瀬戸内海の児島湾に流れ込んでいる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1300X1600)282KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▲ 秀家が岡山城を築城した際、城の防御のために城の北面から東面に添わせるように旭川の流路を蛇行させ、それまでの流路よりも西に付け替えた。流路の不自然な蛇行と、上流域で盛んであったたたら製鉄のための樹木の伐採による山の荒廃や製鉄の工程である「かんな流し」による河床の上昇などの要因によって、岡山城下では度々洪水に見舞われるようになった。 |
|
|
江戸時代に入り、岡山藩主・池田光政のもとに仕えていた陽明学者・熊沢蕃山(くまざわ・ばんざん)が「川除けの法」を考案し、百間川(ひゃっけんがわ)を開削して治水対策が講ぜられた。百間川は操山(みさおやま)の北麓に添うように流れ、東岡山地区から南流して児島湾に注ぐ、全長12.9km、川幅約200mの放水路である。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1800X1450)489KB
|
|
|
|