|
|
|
|
|
| |
水温は10度であるが気温は5度と厳しい。濡れた体では体感温度は更に低く、体は少し赤みを帯びている。水槽から出ると再び「鳥船(とりふね)」「雄健(おたけび)」「雄詰(おころび)」「気吹(いぶき)」の順に行(ぎょう)を繰り返す。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1300x861)181KB |
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(12990x861)197KB |
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1249x828)125KB |
|
|
|
|
|
|
| |
各行の合間には振魂(ふりたま)を行う。振魂は手の中に少しの空間を作るように両手を合わせ、中央に構えて上下に振動させる。振魂をすると神様から霊威が降り注がれ、身体と魂が調和して邪念が振り祓われるという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1250x828)124KB |
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1250X828)141KB |
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1300x861)179KB |
|
|
|
|
|
|
| |
禊場の周りは大勢のアマチュアカメラマンが取り囲んでいるが、無言でシャッターを切る。神聖な場所での私語は慎むのがマナーなのである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1250x812)160KB |
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1250x875)183KB |
|
|
|
|
雄詰 |
の姿勢から右手を「イエーィ」と振り下ろす |
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1200x836)156KB |
|
|
|
|
|
|
| |
境内でのランニングから約20分ほどで全ての行事が終了した。最後に全員が禊場正面にある神祠(しんし)に向かって、二礼、二拍手、一礼して禊場をあとにした。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1300x861)223KB |
|
|
|
|
|
|
| |
境内には火が焚かれているが、禊が終わると一層激しく焚かれた。参加者は燃え盛る炎を背に冷えた体を温めていたが、しばらくして社務所に戻り、着替えをしてから用意されていた昼食を食べて帰って行った。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1250x828)198KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
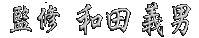 |
|
|
|
|
|
撮影 ・ 原作 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
住居:
岡山県 |
|
趣味:
フィットネスクラブでの運動 水泳等 |
|
|
|
座右の銘: 「継続は力なり」 「歳月人を待たず」 座右の書: 「菜の花の沖」 司馬遼太郎 |
|
|
|
|
|
春日神社の大寒みそぎは昭和52年(1977)に禊所を開所して、30年近くも続いている。当初は参加者も少なかったが、最近ではテレビや新聞などにより防府市だけでなく県外に知れ渡り、今では毎回大勢の人が参加するようになったとのこと。 |
|
今年一回目のみそぎでは防府市長(松浦正人市長)自ら褌一丁で参加したと聞いた。人それぞれが一年間の無病息災を願ってみそぎをする姿は美しい。タオルさえ持参すれば誰でも参加出来るとのことだが、社務所受付に宮司より参加者向けの心構えが貼られている。その冒頭に、「みそぎとは水の霊力により身を清める神事。「身を削ぐ」ともいわれ、自分を厳しく鍛えることによって強く健全な心身をつくる「行(ぎょう)」です。したがって中途半端な気持ちで参加してはなりません。」と戒めの言葉があった。
|
|
平成18年(2006)1月21日撮影 ニコンD70 632枚(897MB) |
|
|
|
感動写真集〈 第209集 〉/日本の裸祭り〈第197集/104種〉「春日神社大寒みそぎ」 |
|
撮影・原作:ちばあきお 監修: 和田義男 |
平成27年(2015)6月8日
作品:第13作
画像:(大26+小11=37)
頁数:4 ファイル数:83
ファイル容量:10MB
平成12年(2000)〜平成27年(2015) 作品数:493 頁数:2,009 ファイル数:92,019 ファイル容量:19,231MB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真/準備運動の雄詰(1250x828)204KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本日、ちば☆フォトギャラリー名作シリーズ第二弾・感動写真集第17作「春日神社大寒みそぎ(復刻版)」が完成した。
この作品は、拡大写真も最後の1枚を除いて全て復元できた数少ないケースである。監修にあたっては、なるべく、原作者の意図を尊重したが、一部、加筆したところもある。 |
|
★☆★彡 |
 |
山口県防府市の春日神社は、専用の禊場があり、大寒みそぎは、大寒の1月20日から3日間、計8回行われるという。子供たちも寒さにめげずに参加しており、佐伯博祥宮司自らが道彦として毎回率先垂範しておられるので、地元市民から幅広く支持され、県外からの参加者も増えているらしく、伝統の裸褌文化として着実に歴史を刻んでいることに感動する。
禊褌も貸与されるようなので、タオルを持参すれば誰でも気軽に参加できるのが素晴らしい。 |
|
私は、毎年、正月第二日曜日に催行される鐵砲洲寒中水浴(東京都中央区)に参加しているので、春日神社大寒みそぎが川面流(かわつらりゅう)の禊行法により行われていることが直ぐに分かった。ただ、細部にわたっては禊指導者である道彦(みちひこ)の考え方によって差異があり、春日神社では、禊ぎ中は合掌していた。鐵砲洲では、振魂(ふりたま)を続ける。寒さを凌ぐことを主眼にすれば、振魂だし、祈りを主眼とすれば合掌なのだろう。
|
|
|
更に細部を見れば、春日神社では、神紋の蔦紋(つたもん)を中央にあしらった鉢巻が貸与され、禊では定番の後ろ鉢巻にして一重(ひとえ)に結んでいた。これで十分に固定されるので、私は一重を好む。 |
|
過去に神社の禊を取材した作品は、かなりある。八海山滝行(新潟県魚沼市)、出羽三山神社湯殿山滝行(山形県鶴岡市)、石浦神社元旦禊(石川県金沢市)、鹿島神宮大寒禊(茨城県鹿嶋市)、鐵砲洲稲荷神社寒中水浴(東京都中央区)、武州御嶽山滝行(東京都青梅市)、玉前神社大寒禊(千葉県上総一ノ宮)、高良大社へこかき祭(福岡県久留米市)、青島神社裸参り(宮崎県宮崎市)など、北から南までかなりの数に上る。 |
今回、山口県防府市の春日神社大寒禊が加わった。全国には、まだまだ多くの禊が行われている。お寺の禊も神社に負けてはいない。これからもできる限り全国の禊文化を収録してゆきたい。〈
完 〉
2015年6月8日 監修 和田義男 |
|
|
|
|
|
