|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
展望台
|
|
|
|
和田家住宅のそばを通り、白川村の北に位置する城山への坂を上り、展望台に立った。太陽が南中し、ちょうど逆光となったが、稲田は一部を残して刈田(かりた)となっている。残された株から芽が出て青く見える田が散在する。これを 田(ひつぢだ 稲孫田)という。 田(ひつぢだ 稲孫田)という。 (ひつぢ)という漢字はフォントが存在しないので、作成した。 (ひつぢ)という漢字はフォントが存在しないので、作成した。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
展望台からの眺め
|
|

|
|
拡大写真(1600X1200)278KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南北の棟の家
|
|
|
|
白川郷の家屋は棟(むね)が南北に沿うように建てられている。
強い季節風の風向にあわせて風の抵抗を最小限にするとともに、屋根に当たる日照量を減らし、夏涼しく冬保温されるという長年の経験による知恵だという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1600X1200)302KB
|
|
|
|
|
|
合掌造り集落 |
|

|
|
拡大写真(955X1600)317KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
明善寺は今から約260年前の寛延元年(1748)に創立された浄土真宗の寺で、本堂、鐘楼門、庫裡(くり)ともに茅葺き(かやぶき)の寺は、全国的にも珍しいという。 |
|
|
|
中でも約200年前の江戸時代に建てられた五階建ての庫裏は、白川村最大の合掌造りであり、郷土館として古い農機具や民具などが展示されている。本堂は村指定重要文化財、庫裏と鐘楼門は県指定重要文化財。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
明善寺本堂(奥)と庫裏(中央)
|
|

|
|
拡大写真(1200X900)265KB
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1024X900)256KB
|
|
|
|
明善寺本堂の妻 |
|

|
|
拡大写真(1024X900)299KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山門と鐘楼を組み合わせた鐘楼門は、屋根を茅葺きとし、寄棟造りの二階建てで、一階に板庇(いたびさし)をつけた珍しい建物である。そばに県指定天然記念物のイチイ(一位)の木(目通し廻り3.5m 樹高10.6m)がある。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1200x900)350KB
|
|
|
|
明善寺本堂 |
|
本堂は庫裏から出入りするためか、木戸で締め切られていた。 |
|

|
|
拡大写真(1200x900)278KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
撮影 2004年10月7日
《 OLYMPUS E-1 》
14-54mm
50-200mm EC-14
500万画素
500枚 570MB
|
|
|
今年冬と秋の二度にわたり白川郷を訪れた。解説は前作「雪の白川郷」に詳しい。今回は、秋と冬の対比を主眼として編集した。 |
|
白川郷の秋は、稲の刈り取りも殆ど終わり、どぶろく祭のあと、冬ごもりに入る。 |
|
半年の間、厳しい冬の中で生活する知恵が詰まっている白川郷。それが世界文化遺産という評価につながった。しかし、厳しい人々の暮らしが遺産と共にあることを忘れてはならない。 |
|
|
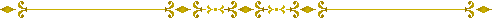 |
|
|
|
白川郷には現在も世界遺産とともに暮らす人々がいます。殆ど昔のままの設備です。庫裡の囲炉裏の間にテレビはありませんでした。合掌屋にアンテナがあるのはおかしいのでしょう。
洗濯物も大っぴらには干せません。我々のように冷暖房完備の快適さからはほど遠い生活です。 |
|
それでも、庄川の電源開発のお陰で国道が整備され、世界遺産になってからにわかに観光客が来るようになり、お陰で地元の若者の就業機会が増え、典型的な過疎の村から一転して日本一美しく、そして豊かで希望のある村作りを目指すことができるようになりました。 |
|
◆ ◆ ◆ |
私が行ったときに、建設中の民家が一軒ありました。
http://wadaphoto5.web.infoseek.co.jp/images/akisirak01l.jpg
の写真中央に写っています。展望台から見ると、その家が建ったためにうしろの合掌屋が隠れてしまっています。我々観光客は、遺跡のように、全く手つかずのままの景観を保存して欲しいと願いますが、地元住民にとっては大変なことだと思います。 |
|
新築中の家は合掌屋ではなく、普通の民家のようです。残念に思いますが、彼らにも現代文明の恩恵を受けた快適な生活を求める権利があると思います。だから建築許可が下りたのでしょう。彼らは、生活の場と世界遺産の保存という相反する命題をどう解決するかで、苦悩しているのだと思います。 |
|
観光化のお陰で、合掌造りが世界遺産として何とか保存され存続していることだけは間違いありません。あの真冬に、ライトアップを見るためにこのような秘境に大勢が押し寄せます。観光資源としての価値がなければ、誰からも見向きもされず、過疎化が進み、老人の村となり、やがては貴重な合掌屋が朽ち果ててしまうところだったことを考えると、日本が世界に誇る「人の住む世界遺産」としてPRし、世界中から多くの人々が白川村を訪ねてロマンと感動を新たにして欲しいと願わずにはいられません。〈 完 〉 |
|
|
|
|
|