|
|
|
おどりめの あかいはなおの りきゅうげた |
|
Aikyu-getas of women dancers, with a red clog thong. |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
拡大写真(1200x900)215KB
|
|
拡大写真(1200x900)204KB
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
拡大写真(1200x900)185KB
|
|
拡大写真(1024x768)149KB
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
拡大写真(1200x900)144KB
|
|
拡大写真(1200x900)154KB
|
|
|
|
|
|
|
よふけまで ろうにゃくなんにょの おどりのわ |
|
Dancing
circles
young and old
until late-night. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
わっしょい!深川祭 |
|
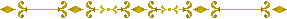 |
|
富岡八幡宮 |
|
東京都江東区富岡 |
|
平成17年(2005)8月12日(金)〜15日(日) |
|
撮影・制作:和田義男 |
|
|
|
|
|
|
|
なつまつり かざすはながさ きやりうた |
|
Summer festival, Kiyari song shading his face with flower bamboo hat. |
|
|
平成17年(2005)8月12日(金)から15日(日)の間、東京都江東区富岡一丁目に鎮座する富岡八幡宮の3年に一度の本祭りである例大祭が開催され、14日(土)の神輿連合渡御を取材した。古くから深川八幡祭(深川祭)と呼ばれ、江戸三大祭りの一つに数えられている。江戸時代から「神輿(みこし)深川、山車(だし)神田、だだっぴろいは山王様」といわれ、神輿祭(みこしまつり)として名を馳せてきた。 |
|
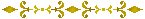 |
|
東京都江東区富岡一丁目に鎮座する富岡八幡宮は、寛永4年(1627)永代島(えいたいじま)周辺の砂州一帯を埋め立て、約六万五百坪(20万m2)の社有地を得て創建された江戸最大の八幡神社で、「深川の八幡様」と親しまれてきた。祭神は応神天皇(誉田別命 ほんだわけのみこと ) 外八柱である。 |
|
江戸時代には、源氏の氏神である八幡大神(はちまんしん、やはたのかみ)を尊崇した徳川将軍家の手厚い保護を受け、明治維新に際しては准勅祭社になるなど、今日まで繁栄してきたが、特に、庶民の信仰は、江戸時代から現代に至るまで変わることなく受け継がれ、毎月1日、15日、28日の月次祭は縁日として賑わいを見せている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
深川八幡宮を目指す神輿 / 駒番八:東陽二 |
|

|
|
拡大写真(1400X1050)410KB
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ 江戸時代、深川に屋敷があった豪商・紀伊国屋文左衛門(きのくにや・ぶんざえもん)から八幡造り・神明造り・春日造りの三基三様の神輿が奉納され、日本一の大きさを誇る絢爛豪華な神輿が評判となって「みこし深川」と云われるようになった。 |
|
|
斎藤月岑(さいとうげっしん)の「東都歳時記」によれば、江戸期の深川祭には12〜13台の山車や練り物が曳き出されていたようで、「八月十五日富賀岡(富岡)八幡宮祭禮」の絵図には、紀文の三基の神輿が描かれている。 |
|
| 紀文の三基の神輿は、惜しくも大正12年(1923)の関東大震災で全て灰燼(かいじん)となり、以来、御本社神輿の復活は深川っ子の悲願であったが、平成3年(1991)と平成9年(1997)に、それぞれ一の宮と二の宮の神輿が奉納され、日本最大の黄金神輿が出現した。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
御本社一の宮神輿 |
|
御本社二の宮神輿 |
|
高さ:14尺5寸(4m39cm) 屋根幅:9尺5寸(2m89cm) 重量:約4.5ton |
|
高さ:10尺8寸(3m27cm) 屋根幅:7尺5寸(2m27cm) 重量:約2.0ton |
鳳凰の胸 ダイヤ7カラット
鳳凰の目 ダイヤ4カラット 1対
鳳凰の鶏冠 ルビー2,010個
狛犬の目 ダイヤ3カラット 2対 |
隅木の目 ダイヤ1カラット 4対
小鳥の目 ダイヤ1カラット 4対
屋 根 純金24kg
その他プラチナ、銀、宝石多数使用 |
|
鳳凰の目 ダイヤ2.5カラット 1対 |
 |
|
 |
|
拡大写真(1050x1400)356KB |
|
拡大写真(1050x1400)348KB |
|
|
|
|
|
|
|
本殿に向かって右奥に明治33年(1900)に建立された横綱力士碑がある。富岡八幡宮では、貞享元年(じょうきょう・がんねん)(1684)幕府の公許を受けて、初めて勧進相撲が行われ、以後年二場所の相撲興業が行われ、江戸勧進相撲発祥の地として知られるようになった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
横綱土俵入之圖 / 第十二代横綱 陣幕久五郎 |
|

|
|
拡大写真(960X1400)239KB
|
|
|
|
|
|
|
| |
▲▼ 初代明石志賀之助(あかし・しがのすけ) 以来の歴代横綱の名が刻まれた横綱力士碑は、第十二代横綱陣幕久五郎(じんまく・きゅうごろう) が発起人となり、各界の協賛を得て奉納されたもの。横綱朝青龍(あさしょうりゅう)も、既に「平成十五年三月 六十八代 モンゴル 朝青龍明徳」と彫り込まれている。なお、大鳥居を入って正面参道の右側には「大関力士碑」が建立されている。 |
|
| |
新横綱が誕生すると、日本相撲協会の立会いのもとに刻名式が行われ、本殿前の石畳の上で新横綱の土俵入りが奉納されるという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総重量20tonに及ぶ横綱力士碑 |
|

|
|
拡大写真(1600X900)330KB
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ 神輿は御神酒所前など要所要所でストップし、神輿を練り上げる。深川不動前も重要なスポットであるらしく、容赦なく水が浴びせかけられる中で、濡れ鼠になりながらも神輿が差し上げられた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成田山・深川不動前で水の集中攻撃 / 駒番七:東陽一 |
|

|
|
拡大写真(1400X1050)465KB
|
|
|
|
|
|
|
ふかがわの みずほとばしる なつまつり |
|
Downtown Fukagawa,
Water splashing
at the summer festival. |
|
|
|
|
成田山・深川不動前の神輿差し / 駒番八:東陽二 |
|

|
|
拡大写真(1400X800)453KB
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ 駒番十九の枝川(えだがわ)の神輿では、堂々と尻からげして赤褌を見せている棒端(ぼうばな)がいた。棒端は担ぎ棒の先端に居る舵取り役で、担ぎ手の兄貴分が担当する。深川にもまだ粋な江戸っ子が健在である。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ぼうばなの まつりふんどし しゅいっぽん |
|
The mikoshi chief porter, wearing a festival loincloth of red sash. |
|
|
|
|
赤褌の棒端 / 駒番十九:枝川 |
|

|
|
拡大写真(1200X1215)375KB
|
|
|
|
|
|
|
|
▲▼ 深川祭の神輿舁(みこしかき)の掛け声は、嬉しいことに「ワッショイ!」で、江戸で唯一伝統が守られているところで、とても嬉しい。鐵砲洲大祭では、弥生会が「ワッショイ!」を取り戻そうとやっきになっている。 |
|
| しかし、その反面、深川祭には「褌禁止」という信じられない掟がある。赤褌の兄貴は、この掟にまっこうから挑戦し、江戸時代の先祖から続く褌を締める勇気ある江戸っ子であり、声援を送りたい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八幡宮前で宙に舞う神輿 / 駒番十三:新川一南 |
|

|
|
拡大写真(1400X1050)408KB
|
|
|
|
|
|
|
|
八幡宮前では、各町会の担ぎ手たちが力を振り絞って神輿を練り上げる。神輿練には、揉み(上下に動かす)・差し(頭上に掲げる)・放り(上に放り投げる)があり、神輿が波のように動くのは見事である。中でも「放り」は重量物を投げ上げる大変危険な技だが、日頃の練習の成果を見せようと、「放り」を披露する神輿がかなりあった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宮前で「放り」を見せる神輿 / 駒番二十一:清澄三北 |
|

|
|
拡大写真(1400X1050)406KB
|
|
|
|
|
|
|
みやまえの なみうつみこし ねりくらべ |
|
Lifting competition
of portable shrines,
waving it
in front of the shrine. |
|
|
|
|
波打つ神輿 / 駒番三十:平野二 |
|

|
|
拡大写真(1400X900)435KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
深川祭/鳳輦渡御 |
|
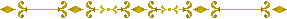 |
|
富岡八幡宮 |
|
東京都江東区富岡 |
|
平成18年(2006)8月13日(日) |
|
撮影・原作:志村清貴 監修:和田義男 |
|
|
|
|
|
|
平成17年(2005)は、3年に1度、大小あわせて120数基の町神輿が担がれ、その内大神輿ばかり54基が勢揃いして連合渡御が行われた本祭り(ほんまつり)の年だったが、陰祭り(かげまつり)の年にあたる平成18年(2006)の8月13日(日)に、二の宮鳳輦の宮出しと町内渡御が行われた。 |
|
富岡八幡宮には元禄時代に豪商として名を馳せた紀伊国屋文左衛門が奉納したといわれる総金張りの宮神輿が三基あったが、惜しくも関東大震災で焼失した。それから68年の時を経て平成3年(1991)に日本―の黄金神輿「一の宮鳳輦」が奉納され、宮神輿が復活した。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一の宮と二の宮の御本社神輿 |
|

|
|
拡大写真(1600X1200)393KB |
|
|
|
|
|
|
|
▲▼ しかし4.5tonもある一の宮鳳輦は、その巨大さゆえに道路通行上さまざまな問題が生じ、奉納のときに一度担がれただけで、その後は展示専用となり、今後も宮出しはあり得ないという。そのため、新たに重量約2tonの宮神輿が製作され、二の宮鳳輦として平成9年(1997)の例祭で披露された。 |
|
|
その後、二度目の宮出しがあったものの、例大祭に担がれることもなく、二の宮鳳輦は一の宮と並んで展示される運命となったが、突然、陰祭りの平成18年(2006)の例祭に三度目の宮出しと町内渡御が行われた。 |
|
二の宮鳳輦の宮出しは、定期的なものではなく、その年々の氏子連合会で決められるので、次回はいつになるかまったく分からない。そのため、今回の宮出し・町内渡御は、神輿フアン垂涎のとても貴重な催しとなった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大鳥居を出る二の宮 |
|

|
|
拡大写真(1400X1024)302KB |
|

