|
|
|
| �@ |
�C���S�@2010.1.15
|
�@ |
|
�� �ߑO11��50���A�����i�т������j�ɔ����Ђ���f���i�Ƃ��傤�j�̔��z�����킦���s�C�҂����́A�������č�����u�ʓ��v�u��ׁv�u�R�̐_�v�u�ٍ��V�v�̏��Ɍ�_�̂�����āu�݂����l�v�ɐ����B�ʓ����A��Ր_�ł���ʈ˕P���̂ЂƂ���傫�Ȗؑ�������Ă���B�吨�̌����q������钆�ŁA���悢��Ղ̃N���C�}�b�N�X�ł���u�C���݂����v���n�܂����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���_�̂�����Đ����S�l�� |
�s�C�� |
�@ 2010.1.15 |
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2200X1830)570KB |
|
|
|
|
|
|
|
�� �l�l�̍s�C�҂��A�u�����I�v�ƈꐺ�i�ЂƂ����j�C���������A���_�̂�����Ȃ���g��������قǂ̌��~�̊C����Ă���э���ł������B�L���L����肤�����ȋF��́A�N���C�}�b�N�X���}���A�}�X�R�~�̎�ސw���l�ӂƑD�ォ��ނ�̉j����ǂ����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2000X1470)318KB |
|
|
|
|
|
|
|
�� ��ސw���悹�������ۂ̑D�ɃG�W�v�g�l�Êw�҂̋g���쎡�T�C�o�[��w�w���̎p���������B�Q��14���i���j�ߌ�S������g�a�b�k�C�������łP���ԕ��f�����u���{�̍Ղ�/�����݂����Ղ�v�̔ԑg�R�����e�C�^�[�Ƃ��ďo�����邽�߂̎�ނł���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@ |
�G�W�v�g�l�Êw�҂̋g���쎡�T�C�o�[��w�w���� |
|

|
|
�g��ʐ^�i2400X1500)419KB |
|
|
|
|
|
|
|
���� �S�l�̍s�C�҂����́A������ɂȂ��Ĕg�ōۂ����10m�̉����܂ł��_�̂�����ĉj���ōs���A��[�����Ԃ������ƁA�ēx�A���֍s���Ă܂������Ԃ��A���̂��Ƃ���܂Ŗ߂��Ă����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��������́@���݂݂̂�����@����̂Ȃ� |
|
Midwinter season, the ablutions of four guardian deities at sea. |
|
|
|
|
|
|
�@ |
�ٍ��V |
�R�̐_ |
��� |
�ʓ� |
|

|
|
�g��ʐ^�i2400X1280)282KB |
|
|
|
|
|
|
|
�� �Ìy�C���������A�Δn�g�������ꍞ��ł��邽�ߓ~�ł���r�I�g�����A���X��������I�z�[�c�N�C�̂悤�ɓ������邱�Ƃ͂Ȃ��B�X�_���̊O�C���ɔ�ׂ�A�ނ���C���ɂ��������y�ł��邱�Ƃ͊m���ŁA�ނ�̗]�T�̕\�������ؖ����Ă���B�������A�������Ƃɂ͕ς�肪�����A������ɂȂ�Ȃ�قNJ����ő̉����ቺ���A�₪�Ă͒�̉��ǂ̊댯�]�[���ɋ߂Â��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
���������Ƃ���܂Ŗ߂��Ă����s�C�҂���
|
|

|
|
�g��ʐ^�i1800X1100)237KB |
|
|
|
|
|
|
|
���� �s�C�҂������A��x���܂ʼnj���ʼn����������A�������炢�̐[���̂Ƃ���ʼn~�w��g�݁A���̒����Ɍ�_�̂��ׂ�ƁA��Ăɐ����悭�C���������āA��_�݂̂̂������s�����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
�g��ʐ^�i1800X1280)375KB |
|
|
|
|
|
|

|
|
�g��ʐ^�i1400X1260)171KB |
|
|
|
|
|
|
|
���� �ʓ��͌�_�݂̂̂������I���ƁA�|�ƂɌ����A������A��l�ʼn��։j���ōs���A�u����ō��N�݂̂����Ղ��ɔ[�߂����Ă��������܂��B�v�Əq�ׂ����A���Ɍ������Ē��A�������A�����i������Łj��ł����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��_�̂���ׂɑ����ĉ��Ɍ������ʓ� |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
���@�ʓ����l�ɖ߂��Ă����Ƃ���ŁA���Ɍ������ĉ����ɕ��сA��_�̂�O�ɂ��āA�S��������ċF���������B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���C�����l�l�s�҂���̔��@�@�k�M |
|
|
�����@��ɂ傤����́@����̂��� |
|
Winter ablution, white of the loincloths of four ascetics. |
|
|
|
|
��_�̂�O�ɍ������� |
�s�C�� |
���� |
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2200X1460)386KB |
|
|
|
|
|
|
|
���@�����߂��I��������ƁA�S�l�̍s�C�҂����́A���l�ɏオ��A���ꂼ��̂��_�̂�^�V�����N�z�ɕ�ݒ����A�݂����l�ł̐_�����I�����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
�����߂��I��������_�̂�^�V�����N�z�ł���݂�����
|
|

|
|
�g��ʐ^�i1400X1150)155KB |
|
|
|
|
|
|
|
�� ����Ē�����́u�C���݂����v���ɏI�����s�C�҂́A�葫����i���сj��Ă���悤�ŁA���瑐���i������j�𗚂����Ƃ��ł����A��y�ɗ������Ă�����ė��i�����j�ɏオ�����B�ʐ^�����́A�R�̐_������s�C�ҁB�����Ⴢ��Ă���悤�ŁA���肵�߂��܂܁A��_�̂�����Ă���p���ɂ܂����B |
|
|
�@�u�݂����v���I�����s�C�҂��]����Q�q�҂̐ɂ��݂Ȃ�����Ɗ��������܂��A�s�C�҂ɑ���[�����h�Ɗ��ӂ̔O��������ꂽ�B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2000X1350)407KB |
|
|
|
|
|
|
|
���@�C���݂������I�������A�s�C�҂����́A�u�݂����l�v�̋߂��ɐ݂���ꂽ�݂����֏�ɂ�����A�O�ڂ̒����A�^���Őg�̂𐴂߂�u������v���I�����B�ŏ��ɁA�ʐ^���̂悤�ɕʓ��ȊO�̂R��������g�ݐ����������ƁA��l���u������v�����A�Ō�́A�ʓ����炪���t���␅�𗁂тāu������v����߂��������B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
�g��ʐ^�i1600X1030)235KB |
|
|
|
|
|
|
|
�@�l�݂̂����̍Ō�ɁA�Q�q�҂ɂ������v�i����₭�j������悤�ɂƁA�ϏO�̓���ɗ␅����܂��ꂽ�B�������鑤�͗₽���Ă����N�������̂œ{��o���҂͂��Ȃ������B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
�g��ʐ^�i1800X1330)335KB |
|
|
|
|
|
|
|
�� �u�݂����l�v�ł̈�A�̐_�����ɏI�����s�C�҂����́A���ꂼ�ꂲ�_�̂�����A��U�T�����ɗ�����������ƁA������_�Ђɖ߂�A�����݂̂����֏�ōŌ�́u������v��������B���̌�A�_�Ж{�a�Ŗ{�Ղ��s���A���Ȃ����J���I�������Ƃ�B���O�_�y�������ɕ��������ƁA�R���Ԃ̂��ׂĂ̍s�����I�������B |
|
|
�u�݂����v�͂��_�̂𐴂߂邾���łȂ��A�s�C�҂ł����Ҏ��g���Ɋ��̎��R�̒��ɐg���N���A�S�g��b���鎎���ł���A���̏C�s���I������҂����́A�l�ԓI�ɂ���i�Ƒ傫����������Ƃ����B |
|
|
|
|
|
|
|
��_�̂�����Ă݂����֏����ɂ���ʓ�
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2000X1200)201KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@ |
|
���ՊۏI�� |
�̒n |
|
�@ |
|
�� �،Ó������A���Պۂ��Â��ɖ��钬�ł�����B�I�����_�Ō������ꂽ���Պۂ́A�������N�i1860�j���C�M���͒��Ƃ��ď�D���A���ďC�D�ʏ����̔�y�����������邽�߁A���Ďg�ߒc��s���悹���A�����J�R�̓|�[�n�^�����̐��s�D�Ƃ��āA���{�D�Ƃ��ď��߂đ����m�����f�����B |
|
�@�����S�N�i1871�j�A�]�˖��{���ۗL���Ă����R�́E���Պۂ����̉����Œ��v�����B���̂��߁A�u���ՊۏI���̔�v����Պۂ̃��j�������g�����Ă��Ă���B |
|
|
|
|
|
|
|
�T���L���̙��Պہi�����͌^�j/�،Ó�������
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2000X1330)431KB |
|
|
|
|
|
|
|
�@�č�����A�҂������Պۂ��A�]�˖��{�̉��ŏ��}�������̒T���Ȃǂ��s�������A�����ېV�̓������̌c��S�N�i1868�j�A�|�{���g�̎w���ŕi�쉫���o�����A�k�C����ڎw�������A�\���ɑ����A��t�����q���ő���ĉ��c�`�ɕY�������B���̌㐴���`�ŏC�������Ă������A�V���{�R�͑��ɕ߂炦���A���̌�͖������{�̖k�C���J��ږ��̗A���D�Ƃ��Ċ����B |
|
|
�����S�N�i1871�j�X��19���i����j�A���˂̔��ɂ������Бq���\�Y�ꑰ401����k�C���ֈڏZ������ړI�Ő��̊������i���Ԃ���j���o�`�A��U���قɊ�`�������Ə��M�Ɍ������r���̂X��20���A�،Ó����T���L�����Ŋ�ʂɏ��グ�č��ʂ��A������ɔj�D���v�����B�K���A�n���̐l�X�̌����ȋ~���ɂ��A��D�҂͑S����ꂽ���A��������P�������S���A�ߗׂ̑�ɑ������ꂽ�B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�ē��̎�����i�E���j�ə��Պۂ����C�悪����B |
|
![���َR��]�ރT���L��](images7/kiko070.jpg)
|
|
|
|
|
|
|
|
�� ���Պۂ������Ă���،Ó����T���L���ɂ́A���Պۂ̈̋Ƃ��]���A���̌��т��㐢�ɓ`���邽�߁u���ՊۏI���̔�v�����Ă��A���Պێq���̉�ɂ��u���Պۂɕ����鎍�v�������Ă���B���̎��̗��ʂɂ́A��䔒�ΕБq�\�Y�Ɛb�c401���̎������L����A�h���Ɣߌ��̋O�Ղ����ǂ������Պۂ̗��j��K���l�X�Ɍ�葱���Ă���B |
|
|
�D�y�s����́A���ՊۍŌ�̏�D�҂��ߍ��ȗ��j�̒��Ŋ����̋������z���đb��z�����Ƃ���ł���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@�T���L���́A���Ă͐ƍ������Ȃ��悤�ȏꏊ�ł��������A���Պۂ̐��܂�̋��ł���I�����_����`���[���b�v�����ꂽ���Ƃ����������ɁA����15�N�i2003�j����Z������̂ƂȂ��ĉԒd�̐������i�߂��A���N�T���Ɂu�T���L���`���[���b�v�t�F�A�v���J�Â���A�`���[���b�v��80��T�������炫�ւ�e���̏ꏊ�ƂȂ��Ă���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
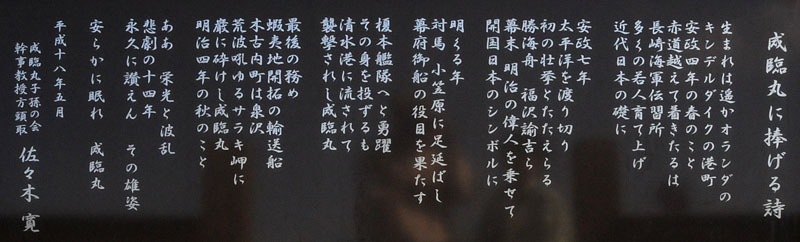
|
|
�g��ʐ^�i1600X485)118KB |
|
|
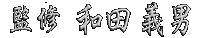
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �B�e�E����F�㕽 ��
�i���݂Ђ�@������j |
|
|
�Z���F�{�茧����s |
|
��F�p�\�R���i�C���^�[�l�b�g�j�A����A�X�L�[ |
|
|
|
|
|
|
|
|
���@�z
|
�@2009�N�S���ɑ�Q�̐l�����̋����قŃX�^�[�g���A���߂ċ��y�̗��j�I�������Ɠ`���|�\�ɃX�|�b�g�����āA�S���̘a�c�t�H�g�t�@���̊F�l�ɏЉ�����ƈӋC����ł��܂������A�Ȃ��Ȃ��ʐ^���B��܂ł̗]�T�����Ă��ɂ����Ƃ���ł����B
�@
�@����Ȓ��A�ȑO���狻���̂������،Ó����́u�����݂����Ղ�v����ނ��邱�Ƃ��ł��܂����B���́u�����݂����Ղ�v�́A�������ɂ�����k���́u�݂����v�Ƃ��ē����͂��Ƃ�荑���ɍL���m���Ă���Ƃ���ł����A�s�u�j���[�X�ŕ��f�����f���́A�s�C�҂������悭�C�ɔ�э���ł����ŏI���̂��̂��قƂ�ǂł���A���̑S�e�͂��܂�m���Ă��܂���ł����B
�@
�@�ŏI���ɍs����u�C���݂����v�́A������͖��_�ł͂���܂����A�{�Ԃ̑O�ɍs����A�̒b�B�����A�{���ɐh�����������̂ł���܂����B�s�C�҂́A�R���ԂŐ��S��̗␅�����Ԃ�܂����A���ɖ�Ԃ̗₦���݂���i�ƌ������A���Ă�������k���钆�ōs���鐅����͈����ŁA�܂��ɖ��������čs���_���ł��B
�@
�@�܂��A�����̒��A�␅�����Ԃ�����̔G�ꂽ�̂̂܂܂ő��҂̐������m�������Ō���邱�Ƃ�A�s�C�҂̐����肪�ꏄ������A�������ƊK�i�����A�_�a�ɓ���Ă��炦���߂��Ă��Ă͂܂���������s���p�ɂ͊������ւ����܂���B
�@
�@�Q�q�҂́A���̂悤�Ȏ�҂����̌������C�s�ɑ���^���Ȏp���瑽���̊�����Ⴂ�A�_�Ћ����ɂ͔ނ���̂���ɂ��݂Ȃ����肪�����n���Ă��܂����B
�@
�@��ނɂ����芦����͏\����������ł������A��܂̓J��������̂��ߎw��̏o����̂��g�p������������A�w�悪�k�C���قł����u�Ȃ܂炵���v���o�ƂȂ�܂������A���̎Q�q�ғ��l�A�����ނ炩�犦���𐁂�����悤�ȑf���炵�����������炢�A�V�N���X�{���ɐ��X�����C�����ɂȂ�܂����B
�@
�@�u�����݂����Ղ�v�ɂ́A�����̔N���҂��l�X�Ȍ`�Ōg����Ă��܂��̂ŁA���ꂩ����ǂ��`�������p����Ă������Ƃ��m�M�����R���Ԃł����B |
|
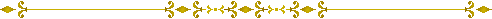
|
|
�Ӂ@�� |
| �@�Ō�ɁA������_�Ж쑺�L�͋{�i�l�A�،Ó����ό�����ɓ����Y�l�A���c���~�l�͂��߁A�u�����݂����Ղ�v���x���Ă�����F�l���̂����͂āA���̍�i�������������Ƃ�S������\���グ�܂��B�L���������܂����B |
| �y��ށz�،Ó����ό�����@�y�Q�l���������z �}�����فE�n���E�w�R�̗��j�i������Ё@���y�o�ŎЁj�A�܂�Ɩ����|�\�i�k�̐������Ɋ��ҏW��c�ҁ@�k�C���V���Ёj�A�t���[�S�Ȏ��T�E�L�y�f�B�A |
|
�������c |
|
�����ʐ^�W�q ��134�W �r�u�،Ó������݂����Ձv |
|
�B�e�E����F�㕽�@���@
�ďC�F �a�c�`�j |
����22�N�i2010�j2��10�� ��i�F��6�� �摜�F�i��69+��13�j �Ő��F5 �t�@�C�����F166 �t�@�C���e�ʁF36.9MB
����12�N�i2000�j�`����22�N�i2010�j�@��i���F354�@�Ő��F1,333�@�t�@�C�����F55,349�@�t�@�C���e�ʁF7,889MB |
|
|
|
|
|
|
|
| �Q�Ă��͘F�����͂ގl�s�� �@�k�M |
|
|
����낤�́@�����������ށ@��傤���� |
|
Four ascetics confining in a shrine, sitting around the fireplace. |
|
|
|
|
�y�ҏW�q���I�Ԗ���z�@ |
|
�͘F���̒Y�Œg�����S�l�� |
�s�C�� |
���� |
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2000X1330)412KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@�����ʐ^�W���l�̏㕽������́A2007�N�X���Ɂu�����̎t�����v�\��A���炭���ق���Ă������A2009�N�S���A���قɖ{�����\�����ĊԂ��Ȃ��j�R��D300���w������A�{���A�Q�N���Ԃ��U��ƂȂ銴�����u�،Ó������݂����Ձv�����������B |
| �@�M�҂�2009�N�V���̋���u����Łu�ʐ^�̓J�������ʂ����́v�Ɖ]�������A�ŐV�Z�p�ɂ�芮������1220����f�̃f�W�J�����A��ʂ̋��X�܂ŃV���[�v�ɕ`�ʂ��Ă����A�㕽����̊����Ƃ����܂��āAinternet�̏펯��j�鋐��Ȏʐ^�𑽗p�����u�،Ó������݂����Ձv�̌���ł�n�邱�Ƃ��ł����B�㕽����̑O��Ƃ͂܂�ň�ۂ��Ⴄ����I�ȍ�i�ŁA�ǎ҂̊F�l�ɐS�䂭�܂Ŕ������摜�����\���Ē�����Ǝv���B����ABGM�́u�݂������ہv����Î҂̖،Ó����ό��������Ē����A�Տꊴ���ӂ���i���ł������������Ƃ����M�������B |
|
 |
|
|
|
�@�،Ó����́u�����݂����Ձv�́A�m��l���m��L���ȗ��ՂŁA���Ƃ���ނł��Ȃ����̂��ƒ����ԉ��߂Ă����e�[�}���������A���̂��сA�㕽��������_�ЂƖ،Ó����ό�����̑S�ʓI�Ȏx���̂��ƂɂR���Ԃɋy�Ԗ�����ނ����s����A���ɂ��̑S�e�\���邱�Ƃ��o�������Ƃ́A��ό��h�Ɏv���B��B�x�X���̐����_����ɑ����A�㕽����ɂ́A�k�C���x�X�������肢���A�����Ƃ���Wa��Da�t�H�g�M�������[����k�C���̑�햡��S���E�ɔ��M���Ē��������B |
|
|
|
|
|
| ���݂����ɓ��ނ锒�ӂǂ� �@�k�M |
|
|
����݂����@���Ԃ��ɂ��ނ�@����ӂǂ� |
|
Midwinter ablutions, the
white
loincloth being frozen by the splash. |
|
|
|
|
�y�ҏW�q���I�Ԗ���z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڂ݂̂��� |
|

|
|
�g��ʐ^�i1600X1063)390KB |
|
|
|
|
|
|
�Ɋ��k���̊����S |
|
�@�u�،Ó������݂����Ձv�́A�͂��S�l�̎�҂��R���Ԋ����S���s���A�ŏI���ɒÌy�C���ŊC���S������Ƃ����ƂĂ��ȑf�ŏ����Ȑ_�����A180�N�Ƃ������j�̏d�݂ƁA�،Ó����グ�Ă̎�g�݂ɂ��A����ҒN�������������ւ����Ȃ��f���炵���~�Ղł���A���̊����x�̍����́A�����قǂł���B |
|
�@�����_�̒��ł�����l�����̐_�ł���ٍ��V�i�ׂ����Ă�j�߂��s�C�҂��A���S�҂ŕ��ʂ̍��Z���ł��邱�Ƃɋ����B�M�҂������s������̓S�C�F��א_�ЂŊ����������o�����Ă��邪�A���̗₽���ɂ͎v�킸��������߂Ă��܂����̂����A�V�l�Ƃ͎v���Ȃ��قǗ��h�ȑԓx�������B�P���̋Ɋ��̖k�C���łS�l�̎�҂����R�Ɨ␅�����A�I�n���̂悤�ȉ��₩�ȕ\������A�܂�Ńv���̏C�Ƒm�̂悤�ɏl�X�Ɗ����݂�������������p�́A�����ɐM�����Ȃ��قǑf���炵���A����l�S�ĂɌ��C�Ɗ������^���Ă��ꂽ�B |
|
|
|
�@�ނ�̈ߑ����\�����Ȃ��B�݂�������A���̑O���Z����i����j�ł��邪�A�������d�˒��߂����Ĉߑ��̗����h���ł���A���ߕ�����{�ɒ����Ŕ������B�ǎ҂́A�_�Ћ����ł́u�݂����v�ł́A�@�����g���̑������g�p���Ă������A�݂����l�ł̖{�Ԃ́A�����@���̑������������Ƃɂ��C�t�����낤���B���̂悤�Ȃ��ߍׂ₩�Ȃ������́A180�N�̓`���̏d�݂ł���Ɠ����ɁA��c����p����������ώ������邱�ƂȂ��p���ł䂱���Ƃ��錈�ӂ̕\��ł���A���̃Z���X�̗ǂ��������Ă���B���V�����̈ꕶ���}�A�߁A�ቺ�ʂ��f���� |
|
|
���������ŁA�]�ˎ��ォ�甲���o���ė����悤�Ȍ��i�����o���ꂽ�B |
|
|
�@�u�،Ó������݂����Ձv�́A�،Ó����̖��`�����������Ɏw�肳��Ă��邪�A���⍑���x���̕������Ƃ��Ẳ��l���\���ɂ���Ǝv����B����A�\�����ĔF��ė~�����Ǝv���B |
|
�@�Ō���A�u�`���̐_�������������̂��߂̊ό������Ƃ����A�������ɂȂ��Ă���v�Ƃ̎w�E�����邱�Ƃɂ��ẮA�M�҂́A�L�`�E���`�̕�������ώ������邱�ƂȂ��㐢�ɓ`���Ă䂯��̂ł���A���������⑺�������̂��߂ɐϋɓI�Ɋ��p���邱�Ƃ́A�n��Z���̓`�������ւ̔F����A�ъ���[�߁A���ړI���������𗬂̗ւ��L������ʂ��傫���̂ŁA�劽�}�ł��邱�Ƃ�t�L�������B |
|
�@�@�@����22�N�i2010�j2��10���@�@ �ďC�@�a�c�`�j |
|
|
|
|
|
|
|
|
�䂫������@�݂������傤��@�������� |
|
Snow geta clogs, a procession for ablutions making a bee line together. |
|
|
|
|
�y�ҏW�q���I�Ԗ���z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�݂����s����o�}���邩�킢���������� |
|

|
|
�g��ʐ^�i2100X1500)512KB |
|
|
|
|