|
|
|
|
|
|
|
|
久留米青年会議所(JCI) |
|
|
|
▼
青年会議所は”明るい豊かな社会”の実現を同じ理想とし、次代の担い手たる責任感をもった20歳から40歳までの指導者たらんとする青年の団体である。久留米青年会議所は、駐車場の北側に建つ大善寺校区公民館(コミュニティーセンター)の二階会議室を拠点として鬼夜に参加している。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
久留米JCIの鬼夜拠点・大善寺校区公民館(コミュニティーセンター)
|
|

|
|
拡大写真(2400x1700)1.12MB |
|
|
|
|
鬼夜を描いた武田弘さんの油絵 / 大善寺校区公民館二階
|
|

|
|
拡大写真(2400x1850)771KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
午後7時前、社務所で横田利幸さんにご紹介頂いた「JCI」の清水辰也さんにお会いし、取材許可を得た。清水さんは、小さいころから玉垂宮の境内を遊び場として育ち、あらゆることに知悉しておられた。 |
|
|
|
現在も御神木の樟樹(楠)に蜷貝(にながい)が生息していることを社務所では知らないといわれたが、清水さんは子供のころから実物を見られており、昼間に写真を撮っておけば良かったと残念に思った。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「JCI」の清水辰也さんと二刀流の筆者 / 大善寺校区公民館二階 2015.01.07 18:53
|
|

|
|
撮影:吉田好幸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
参加者がバスで到着したので、ミーティングが始まり、土肥秀樹理事長の挨拶の後、鬼夜に詳しい清水さんの講話があり、鬼夜の趣旨やポイント、注意点などが披露された。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清水さんの講話によるJCIミーティング 18:49
|
|

|
|
拡大写真(2400x1450)546KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
ミーティングの後、締込みと呼ばれる褌を締めはじめたので、早速、撮影させてもらった。晒一反を前垂れ式六尺褌として締め、余った布を腹巻にする。締めるときにかなり捻りを入れており、前垂れが極端に長い締め方なので、私は鬼夜褌と名付けた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【壱】 19:07
|
|

|
|
拡大写真(2400x1600)447KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● なお、地元では締込みと呼ぶが、国の文化財指定書には、「・・・日暮れとともにタイマツマワシの氏子たちが褌姿で次々と集まり、一同が揃った後大松明の組ごとに神前を流れる霰川で水垢離をとる。・・・」との記述があり、褌と表現しているので、以後、筆者も褌又は鬼夜褌という語を用いる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方
【弐】 〜股をくぐらせてから捻るのがポイント〜
|
|

|
|
撮影:吉田好幸 |
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【参】
|
|

|
|
拡大写真(2000x1150)375KB |
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【四】
|
|

|
|
拡大写真(2000x1150)470KB |
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【五】
|
|

|
|
拡大写真(2000x1150)410KB |
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【六】
|
|

|
|
拡大写真(2000x1150)406KB |
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【七】
|
|

|
|
拡大写真(2000x1150)375KB |
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【八】 〜最後は捻って止める〜
|
|

|
|
拡大写真(2000x1150)400KB |
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【九】 〜前垂れの長い鬼夜褌〜
|
|

|
|
拡大写真(2400x1380)492KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
社務所で長老・幹部たちが着用する鬼夜装束は、鉢巻、締込み、足袋、草鞋だったが、JCIでは、地下足袋を履いていた。昔からの伝統装束ではないが、許容されているのだろう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鬼夜褌の締め方 【拾】 〜
三つ巴の鉢巻を締めて完成!〜 19:22
|
|

|
|
拡大写真(2000x1550)430KB |
撮影:吉田好幸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
JCIのメンバーたちは、6組の大松明に別れて参加する。理事長が二番松明「大善寺」の縄切りをするので、撮影をして欲しいと依頼された。採用されれば機関誌の表紙に使われるという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全員の記念写真 19:35
|
|

|
|
拡大写真(2400x1500)468KB |
撮影:吉田好幸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
午後7時半に惣裁判、棒頭、シャグマが社務所前に集合するので、JCIの撮影を吉田さんにお願いし、公民館を後にした。拝殿に行くと、お参りの人たちが長蛇の列を作っていた。いよいよ夜祭が始まる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拝殿に長蛇の列 19:20
|
|

|
|
拡大写真(2400x1800)734KB |
|
|
|
|
|
|
| |
▼
社務所前では、各地区の惣裁判・棒頭・赭熊(シャグマ)が集まっていた。全員、揃い次第、各地区の持ち場に移動するという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惣裁判・棒頭・赭熊集合 / 社務所前 【壱】 19:22
|
|

|
|
拡大写真(2400x1800)573KB |
|
|
|
|
|
|
| |
赭熊(シャグマ) |
|
| |
▼ 赭熊(シャグマ)は、小学生が木の皮の冠物(かぶりもの)をつけた異様な扮装をして、長さ六尺(180cm)の竹棒を持ち、鬼を警護する役である。午後10時過ぎにこの竹棒で鬼堂の板壁を叩き、鬼堂に籠もる鬼を追い出すと、麻蓑を頭から被った鬼の鬼堂巡り七回り半がはじまる。その後、鬼は、霰川で汐井かき(シオイガキ)をしたあと本殿に入るが、その間、鬼の姿を見られないよう、周りを警護する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惣裁判・棒頭・赭熊集合 / 社務所前
【弐】 〜元気な子供たち〜
|
|

|
|
拡大写真(1800x2000)533KB |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
▼
玉垂宮神紋「左三つ巴」の神紋をつけた防火ヘルメット姿の人が惣裁判(総裁判)で、大松明6組各2人いる。手に樫の棒を持つ。汐井かきから大松明廻しまで、夜祭の全てのシーンでこの姿で奉仕する。この人は、二番松明「大善寺」の惣裁判。汐井かきまでは弓張り提灯を持っているので判別できるが、大松明廻しでは提灯を持たないので、顔を覚えない限り、棒頭(ぼうがしら)と判別できない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惣裁判・棒頭・赭熊集合 / 社務所前
【参】 〜地区ごとに整列〜
|
|

|
|
拡大写真(2000x1500)469KB |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
▼
樫の棒を持ち、玉垂宮神紋「左三つ巴」の神紋をつけた防火ヘルメット姿の人が棒頭で、提灯がない限り、惣裁判と見分けが付かない。棒頭は各組の警護役で、安全な鬼夜の遂行に欠かせない。惣裁判も棒頭も防火ヘルメット姿なのは、大松明の火の粉から身を守るため。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惣裁判・棒頭・赭熊集合 / 社務所前
【四】 〜防火ヘルメットの男たち〜
|
|

|
|
拡大写真(2000x1500)469KB |
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1600x1500)506KB |
|
|
|
|
|
|
| |
▲▼ 鬼の警護役は、かつては棒突(ぼうつき)と呼ばれていたらしく、その特異な被り物を赭熊(シャグマ)ということから、彼らをシャグマと呼ぶようになったという。小学生なら誰でも参加できるので定員はないが、50名ほど参加しないと鬼堂を囲めない。今年は、45人ほど参加したという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惣裁判・棒頭・赭熊集合 / 社務所前
【六】 〜シャグマの前姿〜
|
|

|
|
拡大写真(2000x1750)651KB |
|
|
|
|
|
|
| |
▲▼ 国語辞典によると、赭熊(しゃぐま)は、「 赤く染めたヤクの尾の毛。また、それに似た赤い髪の毛。かつらや兜の飾りなどに用いる」とある。つまり、赤いふさふさしたかつらのことである。なぜ、このような格好をするのか、明確な答えはないが、「筑後の年中行事12ヶ月 篠原正一著」によると、赭熊(シャグマ)は、人の世ともう一つの世界との間を守る存在とされているという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
惣裁判・棒頭・赭熊集合 / 社務所前 【七】
〜シャグマの後ろ姿〜 19:34
|
|

|
|
拡大写真(2000x2100)703KB |
|
|
|
惣裁判・棒頭・赭熊集合 【八】
〜シャグマの記念撮影〜 19:45
|
|

|
|
拡大写真(2400x1900)916KB |
|
|
|
|
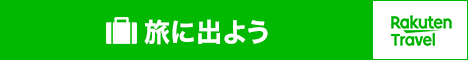
|
|
|
|
|
|
| |
タイマワシ |
|
| |
▼
午後7時半、各地区から本殿裏の神苑の参集場所に裸たち一同が集まり、いよいよ鬼夜の幕が開いた。社務所前の取材を終え、裏参道を通って大善寺の参集場所に行くと、既に地区毎に用意されていた稲藁(いなわら)に火が着けられ、タイマワシと呼ばれる大松明廻し(おおたいまつまわし)を行う裸衆がその周りを囲んで暖を取っていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
タイマワシたちの参集 【壱】 〜大善寺地区の参集〜
19:35
|
|

|
|
拡大写真(2400x1600)643KB |
|
|
|
|
タイマワシたちの参集 【弐】
|
|

|
|
拡大写真(1600x1450)289KB |
|
|
|
|
|
|
はつはるに ふんどししめる おによかな |
|
Ogre's Night wearing fundoshi loincloth in the New Year. |
|
|
|
|
タイマワシたちの参集 【参】
〜小松明に焚き火の火を移す〜
|
|

|
|
拡大写真(2000x1500)478KB |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
▲▼
タイマワシたちが手にしているのが小松明で、午後8時から始まる汐井かき(シオイガキ)の際に大地を清めながら境内を二周する大事なアイテムである。持ち手の方に手を保護する藁が巻かれている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
タイマワシたちの参集 【四】
|
|

|
|
拡大写真(2000x1500)589KB |
|
|
|
|
タイマワシたちの参集 【五】
|
|

|
|
パノラマ写真(2000x1200)402KB |
|
|
|
|
タイマワシたちの参集 【六】
|
|

|
|
拡大写真(1600x1500)367B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
赤い鉢巻を締めている人が赤鉢巻と呼ばれる役で、各組2人の赤鉢巻がタイマワシを指導する重責を担う。この方は第三松明「大橋」の赤鉢巻で、お子さん二人を連れている。子供たちもお父さんと同じ褌(幼児はおむつ)を締め、足袋草鞋も決まっている。その一方で、褌に運動靴のちびっ子や若者も散見されるのは、残念である。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
タイマワシたちの参集 【七】
|
|

|
|
拡大写真(2400x2200)766KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
▼
点火した松明の火を消しているのは、燃え進んで本番の時に短くなってしまうのを防ぐためである。出発の時に再度小松明に点火する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
タイマワシたちの参集 【八】
|
|

|
|
拡大写真(2000x1500)557KB |
|
|
|
